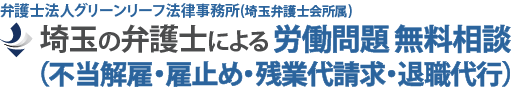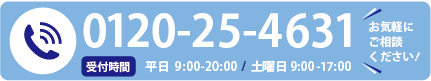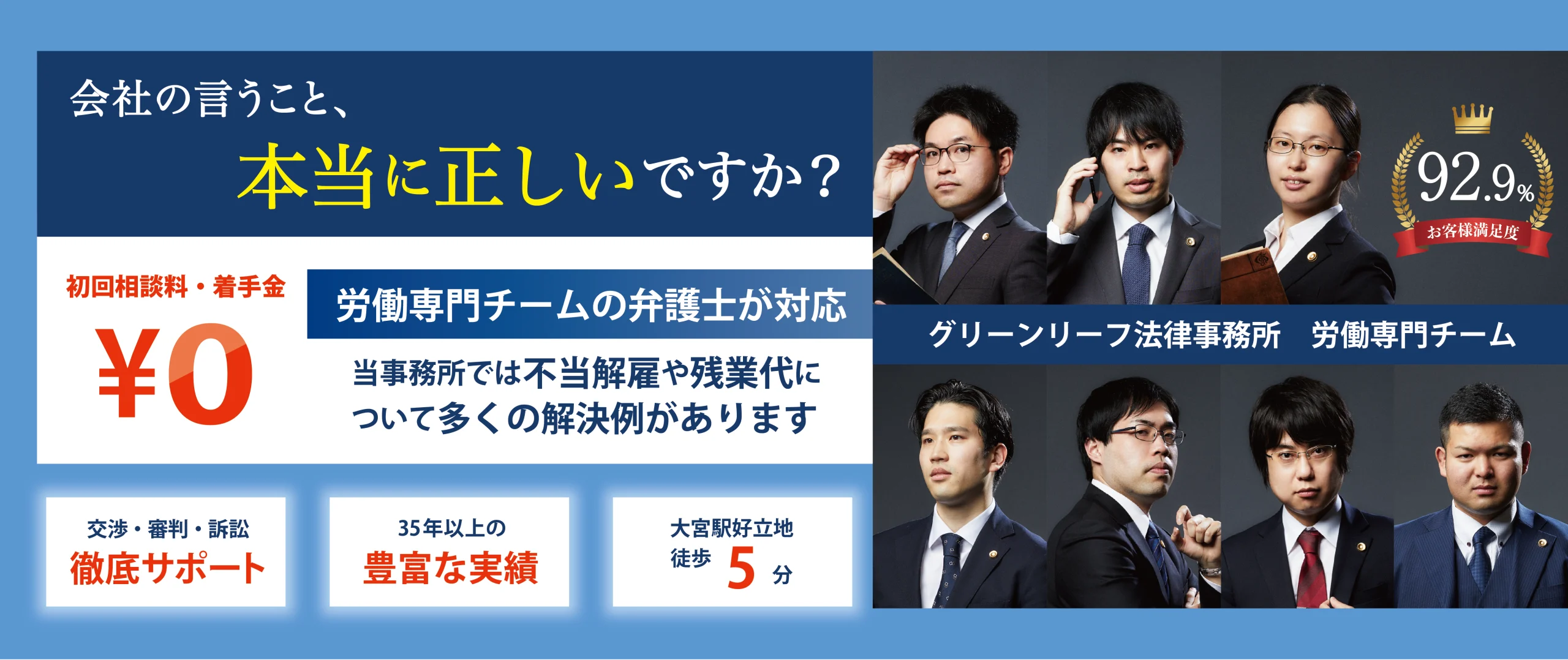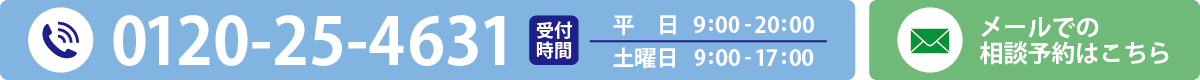「会社を辞めたいけれど、自分では言い出せない」「精神的に限界で、もう出社できない」というような悩みを抱えた方にとって、退職代行は非常に有効な手段です。
しかし一方で、退職代行の仕組みやリスクについて十分に理解せずに依頼してしまうと、思わぬトラブルを招く可能性もあります。
たとえば、「退職したはずなのに離職票が送られてこない」「私物が返却されない」「会社から損害賠償請求を受けた」など、退職後に新たな問題が発生することも少なくありません。ここでは、退職代行の概要や法律的な観点からの注意点、弁護士に依頼する意義などについて詳しく解説し、失敗しない退職のためのアドバイスをお届けします。
退職代行サービスとは?

退職代行とは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスです。
利用者が直接会社とやり取りせずに退職手続を進められる点が大きな魅力ですが、サービス提供主体によって対応可能な範囲が大きく異なります。
現在、退職代行サービスを行うのは大きく以下の3つに分類されます。
- 一般の民間業者によるもの
- 労働組合によるもの(団体交渉権を活用するため厳密には代行とは異なる)
- 弁護士によるもの(法律事務所)
たとえば、民間業者は単に退職の意思を伝えるだけで、会社と法律的な交渉を行うことはできません。これは、弁護士法で定められた「非弁行為」に該当する可能性があるためです。万一、トラブルが発生した場合、民間業者では対応できず、結果的に別途弁護士に依頼せざるを得なくなり、費用と時間がかさむケースもあります。
労働組合が運営する退職代行は、労働組合法によって認められた団体交渉権を活用し、一定の交渉が可能です。
ただし、労働組合であっても、法的な業務を代理することはできませんから、退職の意思表示をする方が、労働組合に加入してその組員として意思表示を行う必要があります。
こうして組合として意思表示を行うとしても、金銭的請求や訴訟対応といった法的手段には限界があるため、法的な交渉や請求を希望する方には弁護士による退職代行が最適です。
弁護士が行う退職代行の強み

法的交渉が可能であること
弁護士は法律上の代理権を有しており、会社との間で法的に意味のある交渉を行うことができます。未払い給与や退職金、有給休暇の消化など、金銭に関する請求も含め、代理人として正式に主張できるため、より実効性の高い対応が可能です。
また、就業規則や雇用契約書に反する不当な対応については、労働法の知識を活用して適切な反論を行い、依頼者の権利を最大限に保護します。たとえば、「退職を申し出たら損害賠償を請求する」といった違法な主張に対しては、法的根拠に基づいてその無効性を明確に主張し、依頼者の不安を取り除きます。
トラブル対応の即応性
たとえば、会社が「辞めるなら損害賠償請求をする」といった脅しをしてきた場合、弁護士であれば法的に無効であることを指摘し、適切に対処できます。精神的に追い詰められている依頼者にとって、法的な盾となる存在があることで大きな安心感が得られます。
さらに、退職に伴って会社から書類が送られてこない、寮を退去する際に敷金が返ってこないなどの金銭トラブルにも、弁護士が交渉・請求を行うことで、スムーズな解決が期待できます。
書面の作成と証拠保全
弁護士が代理した場合、内容証明郵便で退職通知を送付することが一般的ですが、その通知を送った後、その通知自体を証拠として活用することができます。
退職に伴う紛争が発生した際にも、「通知した・受け取った」という証拠の有無が争点になることがあるため、法的な書式を使って通知することは非常に重要です。
このように当初から弁護士に依頼することで、裁判においても後にその証拠を活用することができますし、弁護士からの通知自体に会社側に対して一定のプレッシャーを与える効果もあります。
このように法的な手続きを見越した場合、弁護士に依頼することが良いと考えられます。
利用時の注意点とリスク

非弁行為に注意
弁護士でない民間業者が、報酬を得て法的交渉(賃金請求や退職条件の交渉等)を行った場合、弁護士法違反(非弁行為)に該当します。
依頼者が知らずにそのような業者に依頼した場合、結果として自らの立場を不利にする可能性があります。
加えて、万一損害が発生しても責任の所在が曖昧になり、消費者としての保護も十分に受けられない場合があります。
信頼性と安全性を重視し、法的紛争に備えるのであれば、弁護士に依頼することが重要といえます。
書類トラブルのリスク
退職後、雇用保険の手続きや転職活動に必要な離職票、源泉徴収票などが会社から届かないというトラブルも見受けられます。
弁護士が介入した場合、こうした書類の速やかな交付を促すことも可能です。
特に離職票がなければ、失業給付の申請が遅れることになり、生活に直結する問題となります。法律的な催告を適切な形式で行うことで、会社側の対応を引き出す力となります。
精神的な回復を図る
退職代行を利用する方の中には、うつ病や適応障害などで心身のバランスを崩している方も少なくありません。
そうした方が焦って退職手続を進めようとすると、必要な書類の見落としや将来設計の不備が起きることもあります。
まずは休養と治療を優先し、その上で弁護士と相談しながら慎重に進め、退職の意思表示の窓口を弁護士へ委ねることをおすすめします。
弁護士が対応する退職代行依頼から退職までの一般的な流れ

弁護士に退職代行を依頼した場合、以下のような流れで進行します。
- 初回相談(電話・メール・面談)で現状をヒアリングし、見積りを提示
- 委任契約書の締結と、必要書類(給与明細、雇用契約書等)の提出
- 弁護士名義で退職通知を送付し、会社との対応を一任
- 書類や給与等の交付・精算が完了するまで対応を継続
- トラブルが発生した場合には労働審判や訴訟等の法的手続へ移行も可能
また、必要に応じて社会保険の資格喪失確認通知や健康保険証の返却、退職証明書の発行についても対応を行います。
基本的には、退職の意思表示を行うことのみで問題は解決しますが、仮に法的なトラブルに派生した場合には弁護士でないと対応をすることはできません。
退職代行に付随して、残業代を請求する場合や、その他の請求をして労働審判や訴訟に至る場合(上記5の場合)には、弁護士に対応を依頼することが必要です。
まとめ

退職は労働者の当然の権利であり、会社に遠慮する必要はありません。
とはいえ、精神的に追い詰められた状態での退職手続は、多くの人にとって大きなストレスです。
退職代行という選択肢は、そうした方々にとって有効な手段であり、特に弁護士を通じて行うことで、より安全で確実な結果を得ることができます。
私たち法律事務所では、依頼者の不安に寄り添い、円満かつ迅速な退職の実現をサポートしています。退職を考えているけれど一歩が踏み出せないという方は、ぜひ一度ご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。