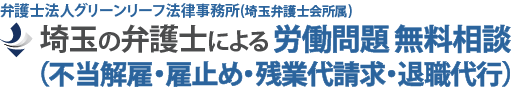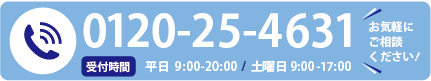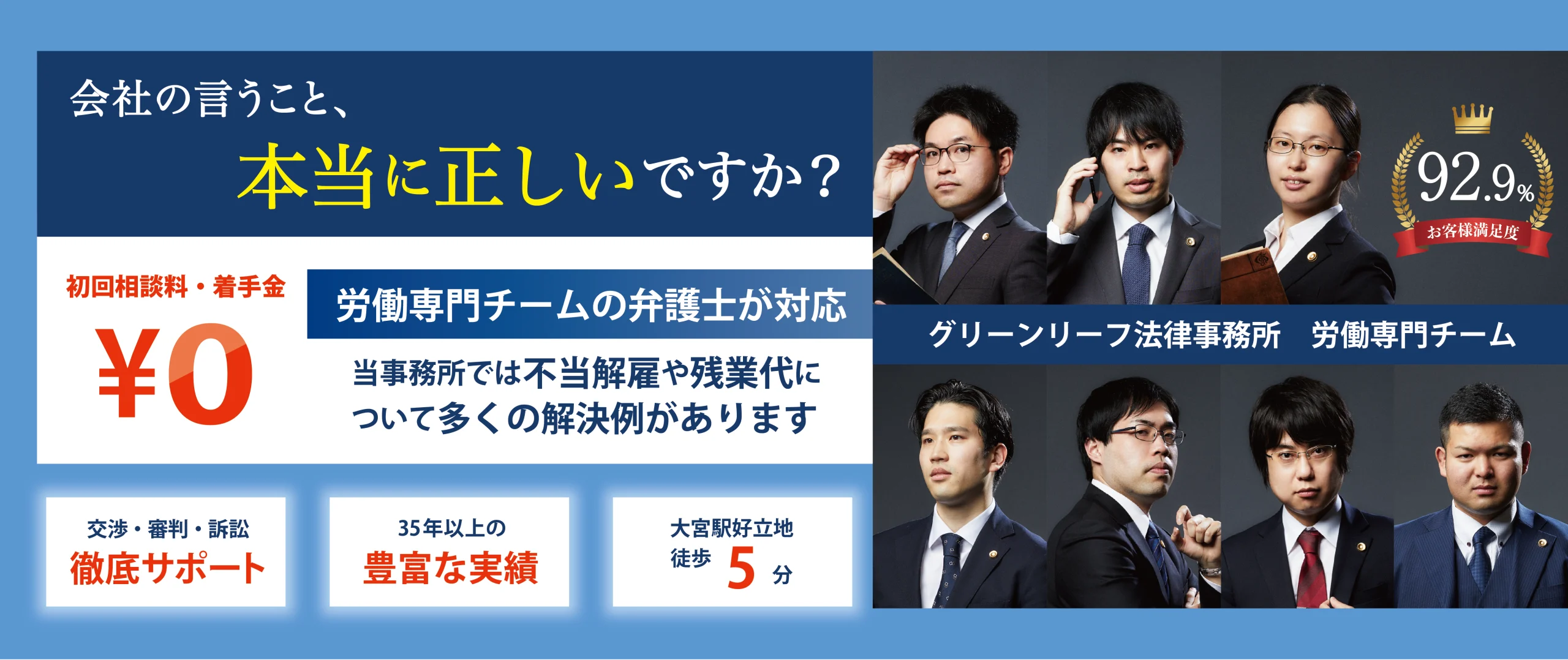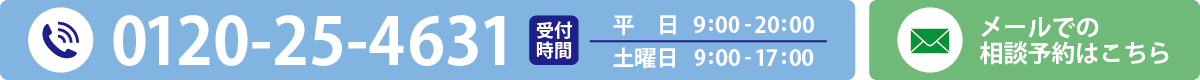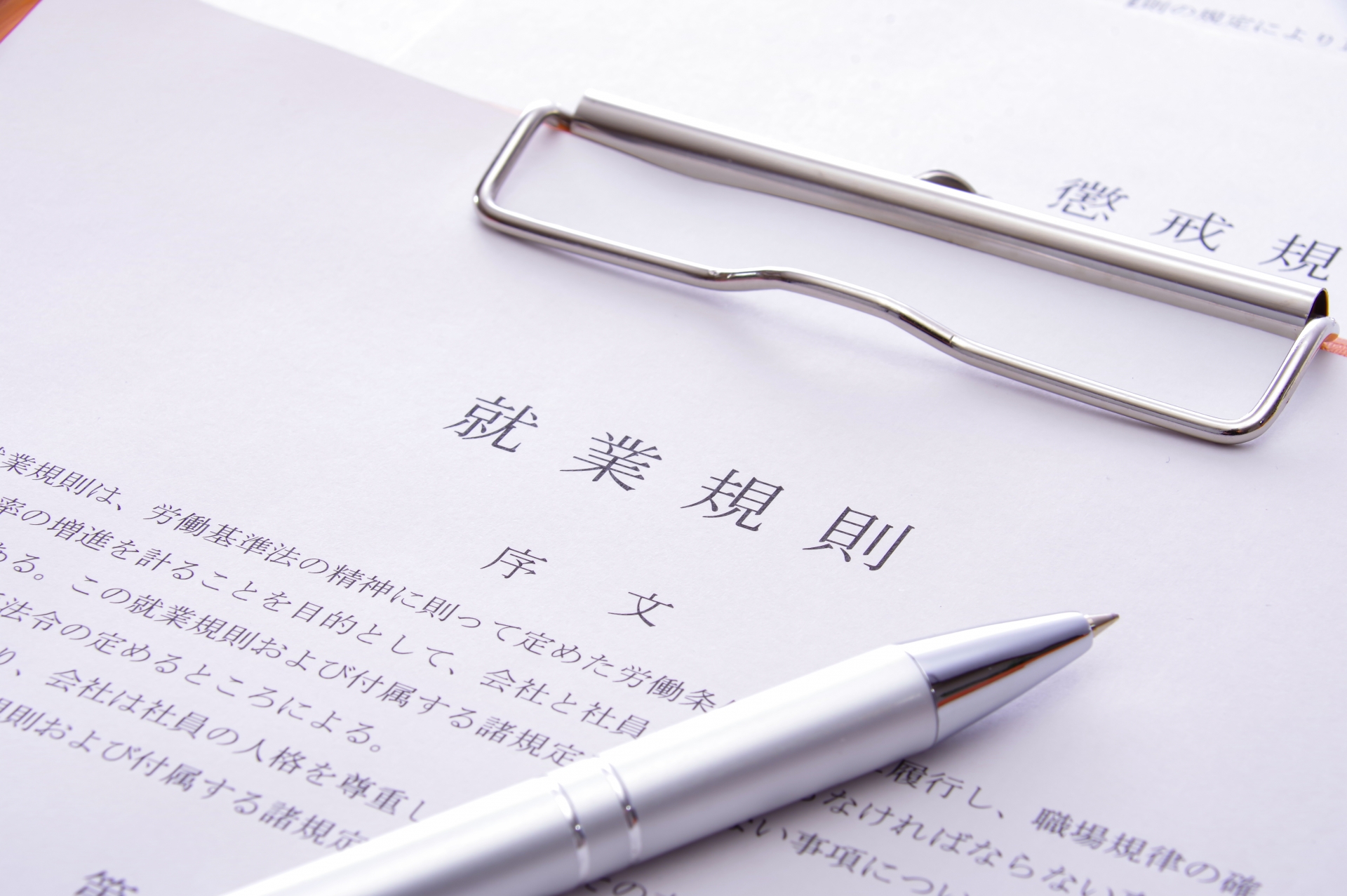
「就業規則が変わったから、給料が減っても仕方がない」「会社の方針だから従ってください」
こういった説明を会社側から受け、不安や不満を抱えながらも諦めてしまう労働者の方は少なくありません。
しかし、労働条件の不利益変更には法律上のルールが存在し、無条件に従う必要はない場面も多くあります。
本コラムでは、労働者の立場から、労働条件の不利益変更とは何か、どういう場合に正当化されるのか、そして争うべきときの手段や証拠の整え方について、解説します。
労働条件と就業規則の関係

労働条件とは、賃金、労働時間、休日、勤務地、退職金など、労働者が労働契約に基づいて提供する労務と、それに対して受け取る待遇のすべてを指します。
これらの労働条件の多くは、個別の雇用契約書だけでなく、会社が定めた就業規則によって規定されている場合が多いです。
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用している事業所において作成と届け出が義務づけられており、会社の内部ルールであると同時に、労働契約の内容として法的拘束力を持つものです。
そのため、就業規則が改定されると、労働者の待遇が変わる可能性がありますが、問題は「労働者にとって不利な方向への変更」が正当化されるかどうかという点です。
不利益変更とは何か?

不利益変更とは、就業規則の変更などによって、労働者にとっての労働条件が悪化することを意味します。
具体例としては、基本給が下がる、通勤手当の廃止、定年年齢の引き下げ、退職金支給条件の厳格化、休日数の削減、勤務場所の遠方への変更などが挙げられます。
これらの変更が一方的に行われた場合、労働者は強い影響を受け、生活にも直結する問題となるため、法律はその有効性について慎重に判断する枠組みを用意しています。
労働契約法第10条による合理性の判断

不利益変更の有効性を判断する際、最も重要になるのが労働契約法第10条の規定です。
この条文では、「就業規則を変更する際、労働者の同意がない場合でも、変更が合理的であるときは、労働契約の内容として変更が有効になる」と趣旨のことを定めています。
ただし「合理的かどうか」は単なる主観ではなく、以下のような具体的要素を総合的に勘案して裁判所が判断します。
まずは、不利益の程度が問われます。たとえば賃金が月額数万円減額されるような重大な変更である場合、合理性は厳しく判断されることになります。
次に、変更の必要性です。企業が経営危機に直面しているなど、変更を行わなければ事業の継続が困難であるといった事情があれば、一定の必要性が認められる可能性があります。
また、変更内容の相当性も重要です。たとえば不利益な変更と見えるものでも、その内容が社会通念に照らして妥当なものであり、労使間のバランスを取るよう工夫されている場合には、合理性が認められる可能性があります。
さらに、労働者に対する代償措置の有無や、変更に至るまでの過程で労働組合などと誠実な協議が行われているかどうかも判断材料となります。透明性を持って変更理由を説明し、労働者との信頼関係を維持する努力がなされていれば、変更の正当性は強まる傾向にあります。
労働者としての対応策
不利益変更が行われた場合、労働者としてはどのように対応すべきでしょうか。
まず重要なのは、自らの意思を明確にすることです。会社が就業規則を変更した際、内容を十分に確認した上で「同意しない」旨をメールや書面で伝えることが大切です。黙っていると黙示の同意とみなされることもあるため、意思表示を残すことが重要です。
次に、変更内容やその周辺の説明資料、通知文、説明会の議事録などをしっかり保存しましょう。後日争う際に、変更の過程が不透明であったことや、必要な説明がされなかったことを立証するための有力な証拠となります。
不利益変更に対して争うための法的手段

このような対応策をとっても改善しない場合、どのようにしたらよいでしょうか。
不利益変更に納得できない場合、具体的に考えられる法的手段はいくつかあります。
任意での交渉
法に違反するよう労働条件の不利益変更は認められるべきではありません。
そこで、不利益変更が認められないということについて、具体的な事実をもとにして主張することが考えられます。
単に、会社に対して「これは不利益変更なので元に戻してください」と個人で主張するだけでは会社が取り合わないこともあります。
そういった場合には、弁護士に相談することが有効な手段といえます。
弁護士が代理人として会社と交渉することで、一定の解決に至る場合があります。
労働審判
次に検討されるのは、「労働審判制度」の活用です。
労働審判は、簡易・迅速に労働紛争を解決することを目的とした制度で、原則として3回以内の期日で審理が終結するという制度です。
裁判よりもスピーディーかつ柔軟な解決が可能なため、不利益変更によって被った損害の回復や変更の無効確認を求める場として有効です。
もっとも、裁判所を用いる手段であることから、申立ての手続きなど法的な知識が必要となります。
そこで、労働審判制度を活用する場合でも弁護士にご相談いただくことが有効です。
民事訴訟
次に、「民事訴訟(労働契約確認請求など)」があります。
就業規則の変更が合理性を欠くとして、労働契約上の労働条件が維持されていることの確認や、不利益変更に基づく損害賠償(減額分の賃金等)の請求を行うことができます。
訴訟は時間と費用がかかるものの、最終的な判断を裁判所に委ねることができる強力な手段です。
また、急迫の危険がある場合には「仮処分申立て」によって、労働条件の変更の効力停止や元の条件での労働継続を求めることも可能です。これは、訴訟の結果を待っていては回復が困難な損害が発生する恐れがある場合に限定的に認められます。
これらの法的手段を選択する際には、証拠の有無が極めて重要になります。変更の経緯、説明内容、影響の程度について、文書・メール・録音など客観的資料を可能な限りそろえることが、勝敗を分ける要因となります。
不利益変更を争う場面では、早期に弁護士に相談することで、自身の立場を整理し、適切な手段を選択することができます。弁護士の介入により、交渉段階での解決が図れるケースも多くありますので、就業規則の変更などでご自身の労働条件が不利益に変わってしまったという方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
まとめ

労働条件の不利益変更は、労働者にとって生活の基盤に関わる重大な問題です。しかし、多くの場合、その変更が本当に正当なものなのか、合理的といえるのかを十分に検討せずに受け入れてしまっている実態があります。
就業規則が変更されたからといって、必ずしも従わなければならないわけではありません。変更の内容・必要性・交渉経緯・代償措置などを丁寧に確認し、少しでも疑問を感じたら専門家に相談することが、泣き寝入りを防ぐ第一歩です。
労働者の権利を守るためには、知識と行動力が不可欠です。不利益変更に直面した際には、ぜひ本コラムを参考にして、納得のいくご判断をしてください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。