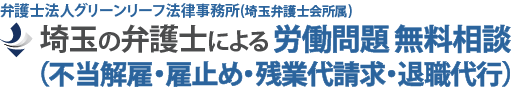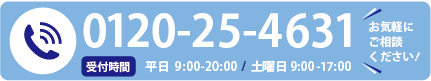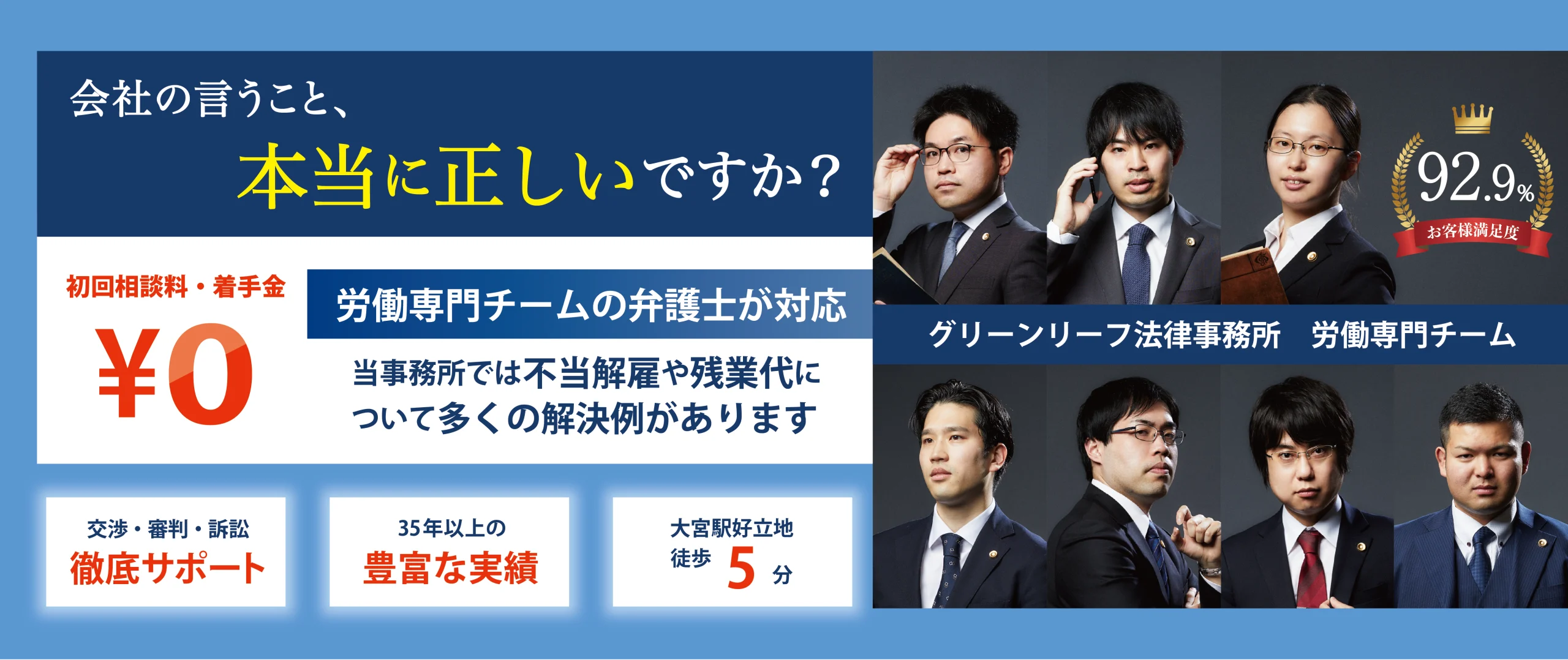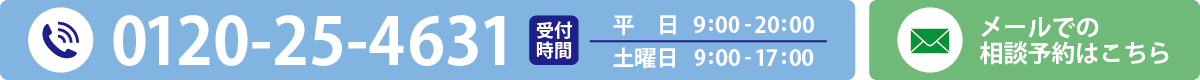会社は、企業秩序違反をした労働者に対し、懲戒処分を行うことがあります。本コラムでは懲戒処分のうち譴責(けんせき)処分とはどのような処分か、また労働者がどのような行為をすると譴責処分がなされる可能性があるのか解説します。
譴責処分とは

譴責処分とは、企業秩序違反をした労働者に始末書を提出させて将来を戒める処分です。
譴責処分は、懲戒処分の中で、戒告と並んで最も軽い処分といえます。
譴責処分のおそれのある行為

一般的に会社の就業規則では、以下のような行為が譴責処分とされていることが多いです。
- 正当な理由のない遅刻や欠勤等
- 正当な理由なく業務命令に従わない
- 各種ハラスメント行為
譴責処分以外の懲戒処分

一般的に、譴責処分以外の懲戒処分として、以下のような処分があります。
戒告
戒告とは、労働者に始末書の提出を求めることなく将来を戒める懲戒処分です。
戒告は、譴責処分と並んで最も軽い懲戒処分です。
減給
減給とは、労働者による労務の提供に対して、労働者が受け取るべき賃金のうち一定額を差し引く懲戒処分です。
減給は、1回の減ずる金額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また総額が一賃金支払い期の賃金の総額の10分の1を超えてはならないと労働基準法91条によって制限されています。
譴責処分の次に軽い懲戒処分です。
出勤停止
出勤停止とは、労働者との労働契約を継続させながら、労働者の就労を一定期間禁止するといった懲戒処分です。「自宅待機」と呼ばれることもあります。
一般的に、出勤停止期間中は賃金が支給されず、その期間を勤続年数に含めないとされることが多いです。
減給の次に軽い処分です。
降格
降格とは、職位や役職を引き下げる懲戒処分です。
諭旨解雇、懲戒解雇に次いで重い処分となります。
諭旨解雇
諭旨解雇とは、会社が、労働者に対し、退職届を提出させた後に解雇する懲戒処分です。
労働者が会社の退職の勧告に従わず退職届を提出しない場合に、懲戒解雇とすることが予定されています。
諭旨解雇は、懲戒解雇と異なり労働者も解雇されることに合意したうえでなされる処分です。
したがって、諭旨解雇は、懲戒解雇に次いで重い処分であるといえます。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、会社が一方的に労働者を解雇する懲戒処分です。
懲戒解雇がなされた場合、就業規則において退職金を全額または一部不支給とする旨定めている企業が少なくありません。
さらに懲戒解雇された労働者は、再就職先を探すことが困難となるおそれがあります。
懲戒解雇は、労働者にとって重大な不利益を及ぼす最も重い懲戒処分であるといえます。
譴責処分されることによって労働者に生じる不利益

譴責処分は、最も軽い懲戒処分です。
譴責処分は、実質的には労働者に対し不利益を課す処分ではありません。
もっとも、昇給、ボーナス、昇格などの場面において、人事考課でマイナス査定となることによって労働者に不利に考慮されることはあり得ます。
退職金について、譴責処分それ自体から直接影響を受けるものではありません。
しかし、譴責処分によって、人事考課がマイナス査定となることで昇給が遅れ、譴責処分がなかった場合と比べて退職金の算定基準となる給与が低くなることによって、結果として退職金が減額されてしまう可能性があります。
また、譴責処分を繰り返した場合、より重い懲戒処分とする旨就業規則に定められている場合もあります。
このように譴責処分が最も軽い懲戒処分であるからといって侮ってはいけないません。
譴責が不当といえる場合

懲戒処分は、懲戒することができる場合において、客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当と認められない場合、当該懲戒処分は、権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法15条)。
すなわち、懲戒処分の一種である譴責処分をすることができる場合ではなかった時や、譴責処分が客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当と認められない場合には、譴責処分は、無効となります。
「懲戒することができる場合」ではなかった
「懲戒をすることができる場合」とは、会社に懲戒権が認められる場合です。
すなわち就業規則において、懲戒の理由となる行為と懲戒の種類及び程度が記載されている必要があります。
したがって譴責処分を行うには、会社の就業規則において、譴責処分の対象となる行為及びその行為が譴責処分の対象となる旨記載されていることが必要です。
客観的に合理的理由を欠いている場合
「懲戒をすることができる場合」であるとしても、当該懲戒処分が客観的に合理的理由を欠いていると認められる場合には、当該懲戒処分は無効となります。
すなわち、当該譴責処分の対象とされた具体的な行為が、就業規則に記載された譴責処分とする行為に該当しないような場合には、当該譴責処分は無効となります。
処分の相当性
懲戒処分に合理的理由があるとしても、当該懲戒処分が、社会通念上相当と認められない場合には、当該懲戒処分は無効となります。
すなわち、当該譴責処分が、労働者が行った行為と比較して、重すぎる処分といえるような場合には、当該譴責処分は無効となります。
まとめ

このように譴責処分は、懲戒処分の中では軽い部類のものですが、処分であることには変わりありません。
ですので、こうした処分の有効性を争って、弁護士を介入させるという事もあり得ます。
また、解雇などの処分がされそうな際に、弁護士を介入させて弁明をすることで、譴責など少しでも軽い処分を獲得すべく働きかけるという事もあり得ます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。