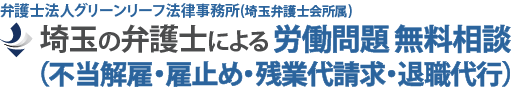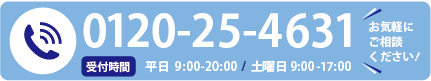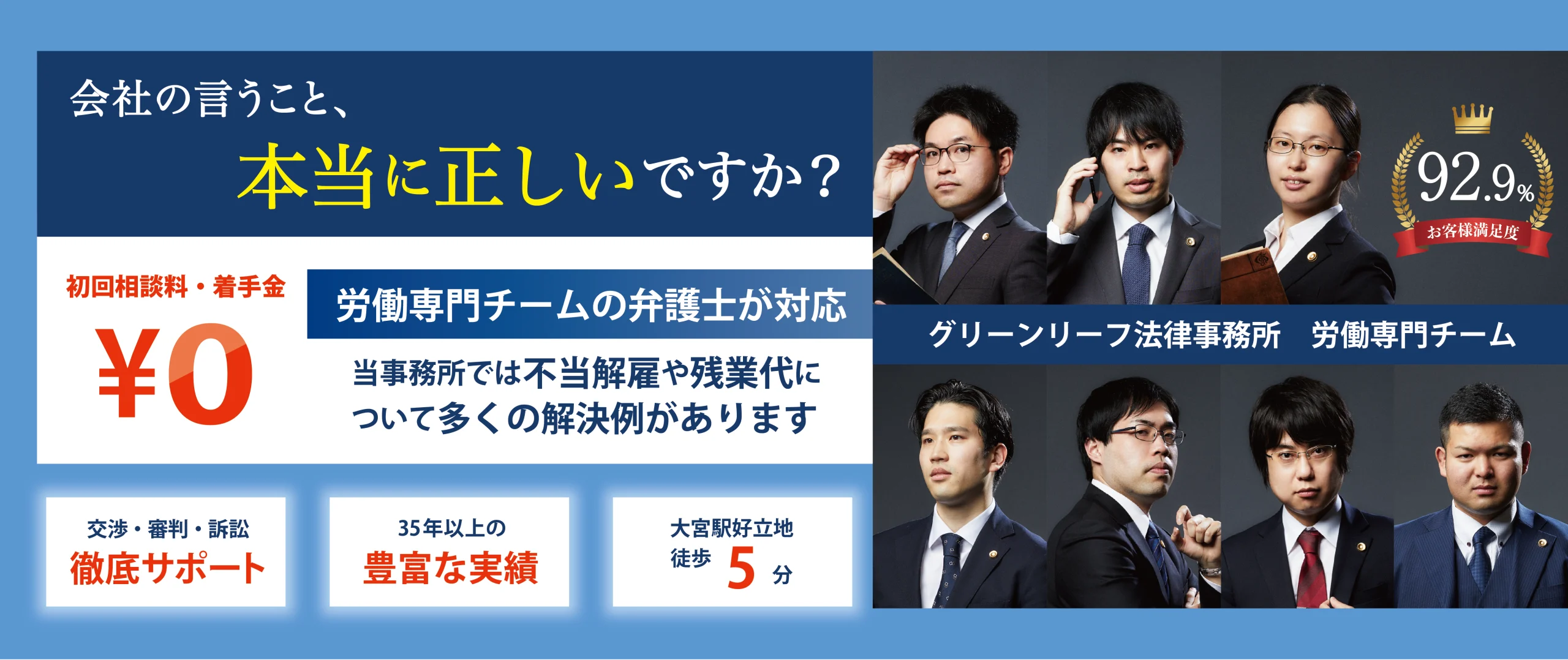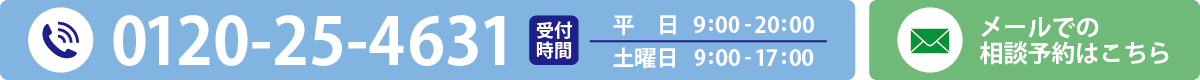ブラック企業の場合、辞めようとしても、会社から無理やり引き止められ、すんなりと辞めさせてもらえないことが多々あります。
このように会社が、労働者が辞めるのを無理やり引き止めることを「在職強要」と呼びます。
本コラムでは、在職強要は許されるのか、在職強要をされているときの対処法について解説します。
在職強要とは

在職強要とは、労働者が会社を辞めようとしているのを、会社が無理やり引き止めることで会社を辞めることができないことを言います。
例えば、「あなたの後任者が見つかるまで辞めさせない」「会社に損害与えているから辞めるなら損害賠償や違約金を請求する」「退職は1年前に言わないと認められない」などと言われ、引き止められるケースが見られます。
また、退職届を出したのに受理してもらえないといったケースも見られます。
そもそもこのような在職強要は、法的に許されるものでしょうか。
在職強要は違法?

労働者は、会社を辞めたいときに自由に辞められるのでしょうか。
雇用形態ごとに分けて確認していきます。
期間の定めのない雇用契約の場合
正社員といった労働者は、契約期間が定められていません。
このような契約期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも退職の申し入れをすることができ、退職の申し入れから2週間経過することによって退職することができます(民法627条1項)。
就業規則で2週間以上前に退職の申し入れをする旨の規定がある場合にはどうでしょうか。
これは非常に難しい問題となっていて、判例や学説でも見解が分かれています。
一般的には、合理的な理由があれば期間の延長が認められるものの、その期間が極端に長い場合には、労働者の退職の自由を過度に侵害しているとして、無効と判断されます。
事案にもよりますが、通常、1か月前に退職の申し入れをしなければならない旨の就業規則であれば、有効と判断されるケースが多いです。
期間の定めのある労働契約の場合
派遣社員や契約社員といった労働者は、「1年間」などといった契約期間が定められています。
このような期間の定めのない雇用契約の場合は、その期間が満了すれば退職することができます。契約期間満了後、契約期間の更新が予定されていることもありますが、それは新たな雇用契約ということになりますので、契約期間の更新を断り、退職することは可能です。
また、契約期間中であっても、「やむを得ない事由」が存在する場合、退職することができます(民法628条)。
「やむを得ない事由」には、労働者自身の心身の病気、親族の介護等がこれに当たると考えられています。
「やむを得ない事由」に当たるかどうかは、個別の事案ごとに判断されますので、自分で判断することが非常に難しいです。自分の場合に「やむを得ない事由」にあたるのか気になりましたら、弁護士にご相談ください!
加えて、契約期間が1年を超えるものである場合、契約期間の初日から1年を経過した日以後はいつでも退職することができます。(労働基準法137条)
対処法

会社は、労働者に対し、様々な手法で引き止めようとしてきます。
このような会社相手に労働者個人1人で立ち向かうことは精神的にとても大変です。
そこで、速やかに退職するためには、専門家に相談することが重要です。
有力な相談先について2つ紹介します。
労働基準監督署
労働基準監督署は、会社が法律をしっかり守っているかチェックするための機関で、必要があれば会社に指導・改善を働きかけることもあります。
会社に対し、労働基準監督署の調査や指導が入ることによって、あなたの在職強要に関する会社の対応が変わることがあります。
弁護士
弁護士は、あなたの代理人として、会社に対し、退職の交渉をすることができます。
弁護士が間に入ることで会社と直接やり取りすることがなくなるため、あなたの精神的負担がとても軽くなります。
また、弁護士は法律の専門家ですので、会社が誤った主張をする場合には、法的な根拠に基づいた的確な反論をすることができます。
加えて、未払いの残業代がある場合や、パワハラ等の問題があった場合には、それらについても併せて会社に責任追及をすることができます。
在職強要に対する弁護士の対応

弁護士は、在職強要に関して依頼を受けると、以下のような対応であなたの退職をサポートします。
まず、早期の退職を実現するために、会社に対し、退職する旨記載のある内容証明郵便を送ります。
併せて、未払いの残業代やパワハラ等による慰謝料の請求を同時にすることもあります。
内容証明を送っても会社の態度が変わらない、そもそも会社から返事が来ないというような交渉で解決することができない場合もあります。
そのような場合には、労働審判や訴訟を申し立てるといった法的な手段を利用することによって、あなたの退職をサポートします。
まとめ
・在職強要とは、労働者の退職を会社が不当に引き止めることを言う
・期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し入れから2週間後に退職できる
・就業規則で1か月程度前の解約の申し入れをしなければならない旨の規定は有効と判断される可能性が高い
・期間の定めのある雇用契約は、雇用の更新が予定されていたとしても、期間満了後、自由に退職することができる
・弁護士は、未払いの残業代や、パワハラ等の問題についても同時に解決することができる
・退職できずお困りの際は、一度弁護士や労働基準監督署に相談を!!
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。