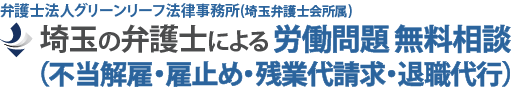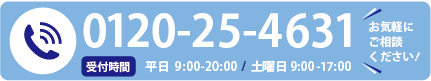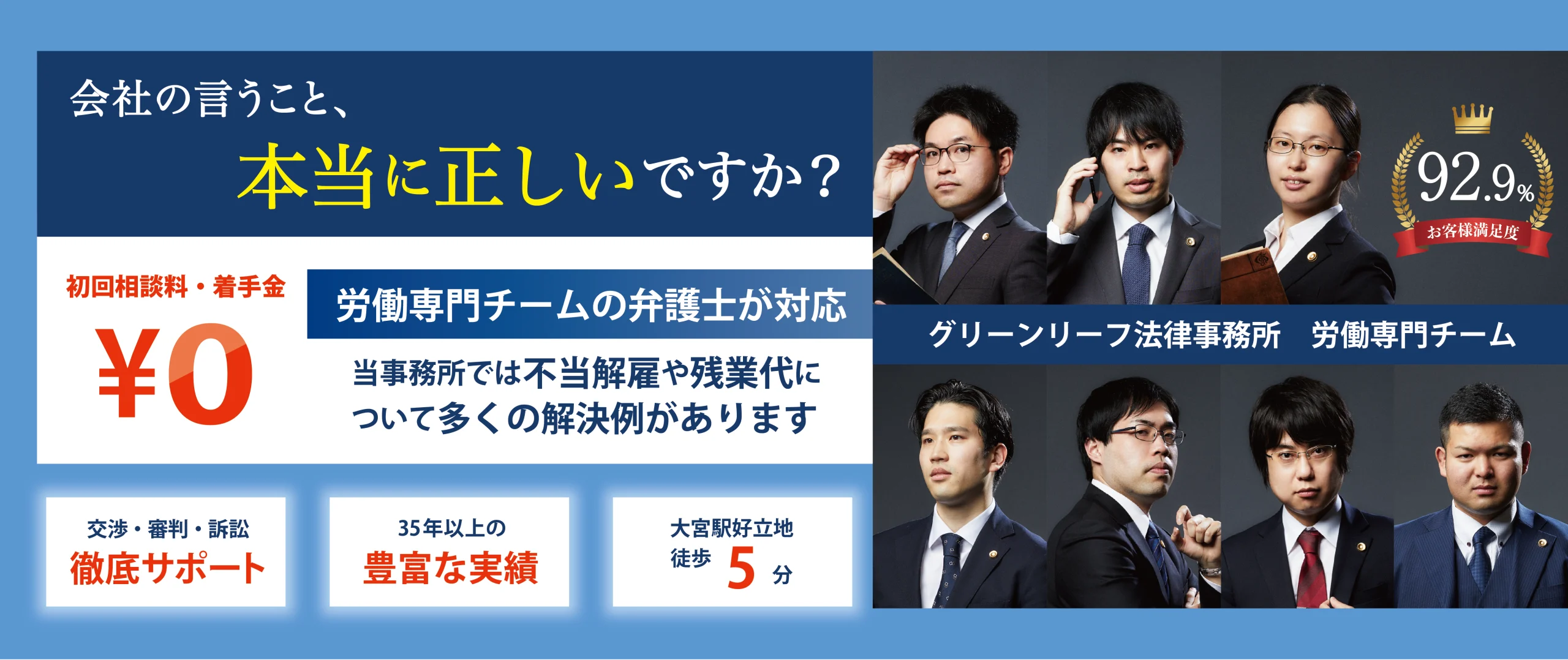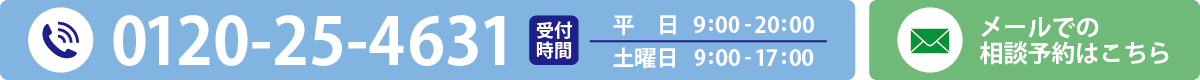多くの労働者にとって、深夜に及ぶ残業は珍しいことではないかもしれません。
しかし、会社から十分な対価、すなわち「残業代」が支払われていないとしたら、それは労働基準法に違反する違法な状態です。
特に「深夜残業」は、通常の残業と異なり、より高い割増賃金が適用されることが法律で定められています。
このコラムでは、「深夜残業している場合、会社に対して残業代を請求できるのか?」というお悩みの方向けに、深夜残業の定義、適正な割増率、請求するための手順、時効の壁等を解説しています。
深夜残業の定義と法律上の義務

1「深夜」の正確な定義
労働基準法において、「深夜」とは午後10時から翌日の午前5時までの時間帯を指します(労働基準法第37条第4項)。
この時間帯に労働者が働いた場合、企業つまり使用者は、通常の賃金に加えて、法律で定められた割増賃金を支払う義務があります。
深夜労働に対する割増賃金は、労働者の健康保護の観点から設けられており、通常の労働時間に対する賃金の25%以上を上乗せしなければなりません。これを一般に「深夜手当」と呼びます。
2. 「深夜残業」とは?
「深夜残業」とは、この深夜の時間帯(22時~翌5時)に、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて労働することを指します。
法定労働時間を超える労働(時間外労働=残業)自体も、割増賃金の対象です。
| 割増の種類 | 適用される労働時間 | 割増率(最低限) |
| 時間外労働(法定時間超) | 法定労働時間を超える労働 | 25%以上 |
| 深夜労働 | 22時〜翌5時の労働 | 25%以上 |
深夜残業の場合、この「時間外労働の割増(25%以上)」と「深夜労働の割増(25%以上)」が重複するため、合計で50%以上の割増率が適用されることになります。
3. 休日労働が深夜に及んだ場合
さらに、法定休日(原則として週1日、または4週を通じて4日)の労働が深夜に及んだ場合、割増率は以下のようになります。
| 割増の種類 | 適用される労働時間 | 割増率(最低限) |
| 法定休日労働 | 法定休日における労働 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 22時〜翌5時の労働 | 25%以上 |
この二つが重なると、合計で60%以上(35% + 25%)の割増率が適用されます。
このように、深夜残業をしている場合、企業は法律に基づき通常の賃金の1.5倍(時間外労働と重複)または1.6倍(法定休日労働と重複)の賃金を支払う義務があり、これらが支払われていなければ、会社に対して未払い残業代として請求する権利があります。
請求権の有無と例外規定
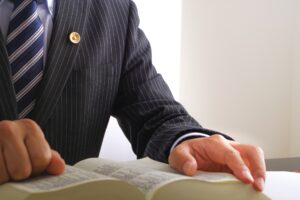
深夜残業の残業代は原則として請求できますが、労働者や労働形態によっては例外が存在するため、自身の状況を確認することが重要です。
1. 残業代請求が可能な「労働者」の範囲
「労働者」とは、簡単に説明しますと、企業に雇用され、指揮命令のもとで働くすべての人を指します。
正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、雇用形態に関わらず、深夜残業をしていれば、その対価として割増賃金を請求できます。
2. 注意すべき「管理監督者」の例外
残業代の支払い義務の例外として、労働基準法上の「管理監督者」が挙げられます。
管理監督者とは、経営者と一体的な立場で労働時間管理から外れた権限を持ち、その地位にふさわしい待遇を受けている者を指します(部長、工場長などの肩書ではなく、実態で判断されます)。
管理監督者には、通常の時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務は原則としてありません。
しかし、ここで重要な例外があります。
仮に、管理監督者であっても、深夜(22時~翌5時)に労働した場合は、その労働に対する25%以上の深夜割増賃金(深夜手当)は支払われなければなりません。
「自分は管理職だから残業代が出ない」と諦めていた方でも、深夜に働いた分については請求できる可能性があるため、請求の可否を判断する際は注意が必要です。
3. その他の例外
業務の性質上、労働時間の配分を労働者に委ねる裁量労働制の場合でも深夜労働の割増賃金は支払われる必要があります。
また、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う固定残業代(みなし残業代)制度について、この制度自体は違法ではありませんが、固定残業時間を超えた深夜残業分、あるいは固定残業代に深夜割増分が含まれていない場合は、別途請求することができます。
未払い残業代請求の具体的な手順

実際に会社に対して未払い残業代を請求するには、手順を踏んで慎重に進める必要があります。
以下では、具体的な手順について解説いたします。
1.証拠の収集
未払い残業代を請求する際、最も重要となるのが「証拠」です。
口頭での主張だけでは会社は応じてくれない可能性が高いため、客観的な証拠を確保することが成功の鍵となります。
集めるべき証拠は以下のものがあります。
労働時間に関する証拠: タイムカードの記録、PCのログイン・ログオフ履歴、業務日報、会社のセキュリティゲートの入退室記録、業務で使用したメールやチャットの送信履歴など
雇用条件に関する証拠: 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則など(深夜残業の規定や賃金計算の基礎を確認するため)
賃金に関する証拠: 給与明細、源泉徴収票、銀行の振込記録など(受け取った賃金と計算上の差額を証明するため)
特に、会社側がデータ隠蔽や改ざんを行う可能性もあるため、これらの証拠はできるだけ速やかに、そして継続的に集めておくべきです。
2. 未払い残業代の計算
収集した証拠に基づき、正確な未払い残業代を計算します。
深夜残業の割増率(1.5倍または1.6倍)を適用して、未払い額を算出します。
時給は、基本給を月平均所定労働時間で割って算出するのが一般的です。
3. 会社への請求
計算した金額に基づき、会社に対して残業代の支払いを請求します。
この際、口頭ではなく、内容証明郵便など、法的な証拠が残る方法で請求することが強く推奨されます。
内容証明郵便の方法で請求することで、後述する時効の完成を一時的に猶予する効果も生じます。
書面には、未払いとなっている期間と金額、根拠となる法律(労働基準法第37条など)を明記します。
4. 会社が応じない場合の選択肢
会社が請求に応じない、または金額に争いがある場合は、以下の法的手段を検討します。
労働審判: 裁判官と労働関係の専門家からなる審判員が間に入り、原則3回以内の期日で解決を図る手続きです。迅速な解決が期待できます。
民事訴訟: 裁判所に訴訟を提起し、判決によって残業代の支払いを命じてもらう手続きです。時間がかかることが多いですが、最終的な解決手段となります。
いずれの手続きも専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することが不可欠です。
残業代請求における「時効」の壁

未払い残業代を請求する上で、最も注意しなければならないのが「時効」です。
1. 残業代請求権の時効期間
労働基準法の改正により、残業代請求権の消滅時効は以下のように定められています。
| 発生日 | 時効期間 |
| 2020年3月31日以前に支払われるべき賃金 | 2年 |
| 2020年4月1日以降に支払われるべき賃金 | 3年(当面の間) |
つまり、現時点では、過去3年間の未払い残業代をさかのぼって請求することが可能です。
2. 時効の「起算点」と「進行」
時効は、未払い残業代が支払われるべきであった給料日の「翌日」から進行します(民法の初日不算入の原則)。
例えば、毎月25日が給料日の場合、5月25日に支払われるべき残業代が未払いだった場合、時効は5月26日から進行し始めます。
時効は毎月(給料日ごと)に個別に進行します。何もしなければ、毎月1日ずつ請求できる権利が消滅していくことになります(ローリングの期限)のでご注意ください。
3. 時効の「完成猶予」と「更新」
時効が迫っている場合、時効の完成を阻止または遅らせる手段があります。
| 手段 | 効果 | 具体的な方法 |
| 完成猶予(6ヶ月) | 時効の完成を一時的に遅らせる | 内容証明郵便による請求(催告) |
| 更新 | 時効の期間をリセットする | 会社が支払いを認めたり(承認)、裁判所の手続き(訴訟・労働審判など)を開始したりする |
時効によって請求権が消滅してしまうと、その後は一切請求できなくなります。
そのため、未払い残業代があると感じたら、速やかに証拠を集め、内容証明郵便で請求を行うなどの「時効の完成猶予」措置を取ることが非常に重要です。
まとめ

深夜残業(22時~翌5時)をしている場合、通常の割増賃金(25%)に加えて、深夜割増賃金(25%)の合計50%以上の割増賃金を受け取る権利があります。
たとえ、管理監督者であっても、深夜労働分の割増賃金は発生します。
深夜にまで及ぶ労働は、肉体的にも精神的にも大きな負担を伴います。その対価が正当に支払われることは、労働者として当然の権利です。このコラムが、あなたの正当な権利を守るための一歩を踏み出す助けとなれば幸いです。
決して一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。