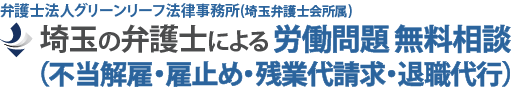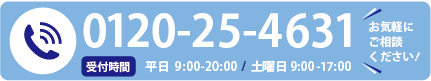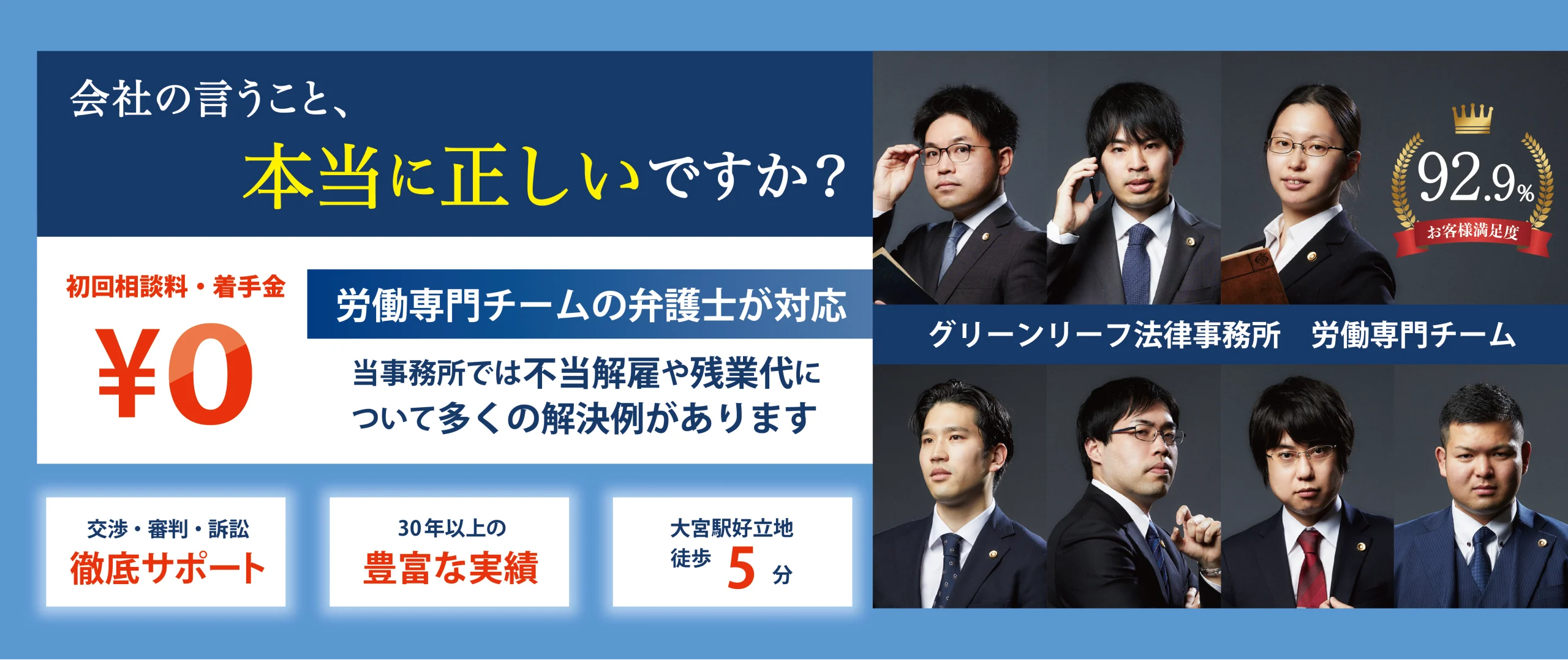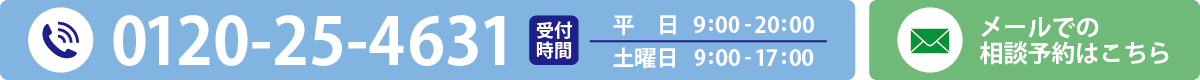そもそもの前提ですが、大切な点なので、改めてまとめておきたいと思います。
まず、使用者は、原則として、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならず、1週間の各日については、休憩時間を除き1日に8時間を超えて労働させてはなりません。また、使用者は、労働時間の合間に休憩時間を付与したり、休日を付与しなければなりません。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分以上、8時間を超える場合には1時間以上でなければなりません(法定労働時間)。
休日については、原則として、毎週少なくとも1回以上でなければなりません(法定休日)。
そして、使用者が、労働時間を延長し、もしくは休日に労働させた場合、又は深夜の時間帯に労働をさせた場合には、通常の労働時間又は労働日の賃金に一定の割増率を乗じた割増賃金を支払わなければなりません。
実は、「残業代」という法律上の概念は存在していません。ただ、一般的には「残業代」とは残業により生じる賃金を指す趣旨の言葉であり、労基法に定める割増賃金がこれに相当することになります。
ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。