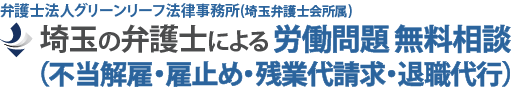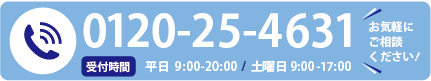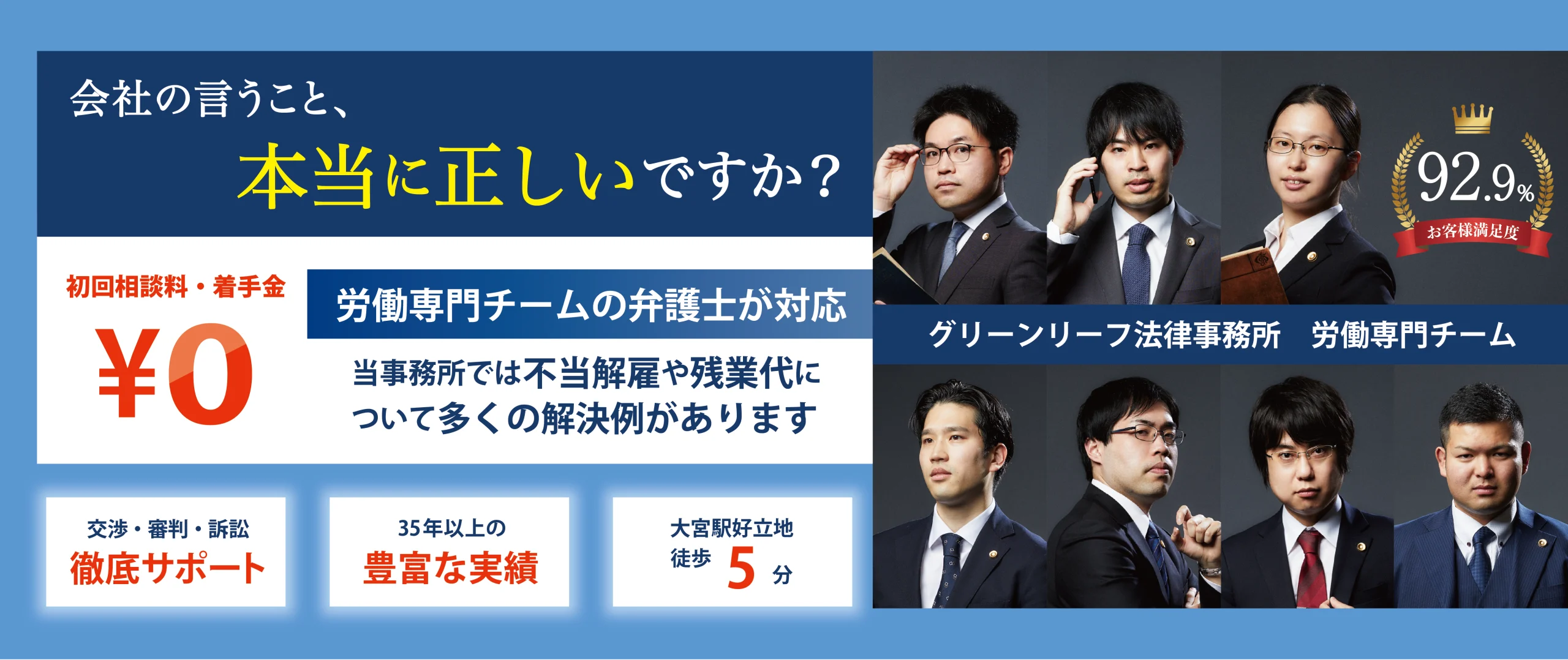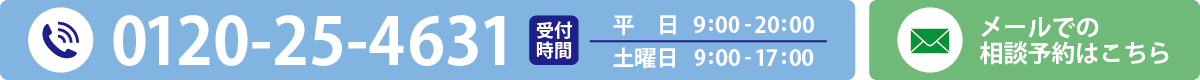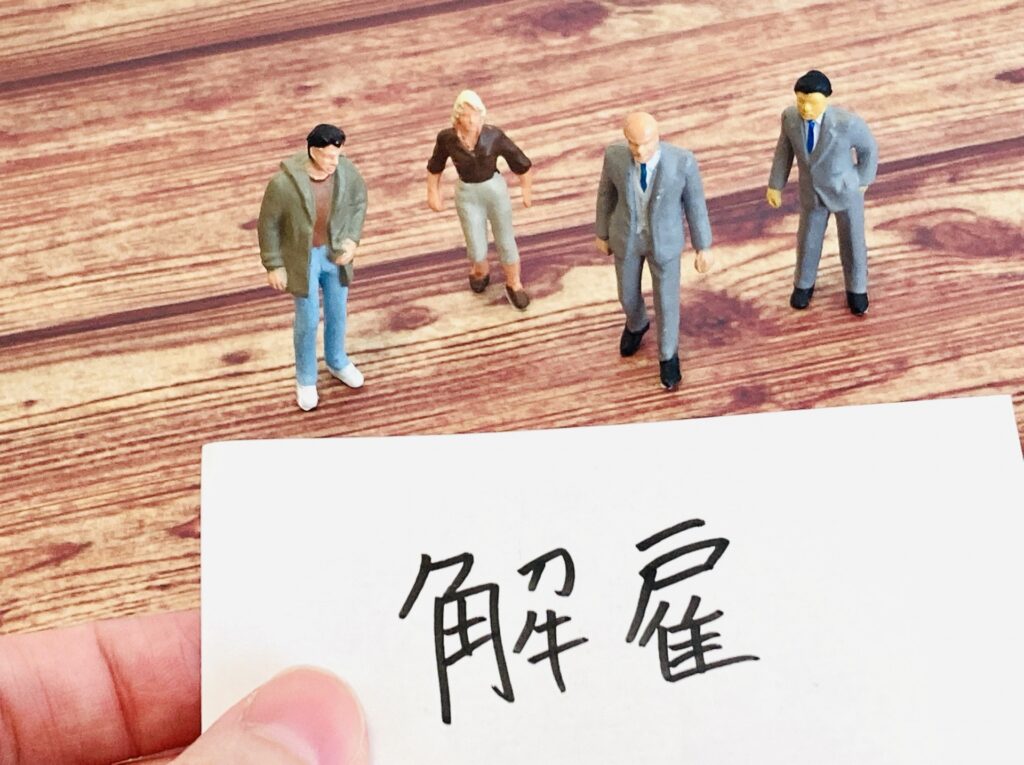
契約社員・パートといった正社員はでない有期雇用契約者にも、「クビ」すなわち雇止めを争うことができる場合があります。本コラムでは、雇止めについての労働契約法上のルールと雇止めに関する裁判例を紹介しながら、どのような場合に争えるかわかりやすく解説します。
雇止めとは? 正社員との違い

契約社員やパートは、契約期間の定められた有期の雇用契約である場合が多いです。
雇止めとは、そのような有期の雇用契約の契約期間満了時に、使用者が契約の更新を拒否し、労働者との雇用関係を終了させることです。
有期の雇用契約の労働者は、期間の定めのない雇用契約である正社員の場合とは異なり契約期間が切れたらそれで終了と思ってしまいがちですが、法律は必ずしも雇止めを許していません。
雇止めにもルールがある ~労働契約法第19条~

労働契約法19条では、以下のような事情がある場合に、雇止めに合理的理由がなく社会通念上の相当性がない場合、会社は、有期の雇用契約の労働者の雇止めをすることができないと規定されています。
- 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること(同条1号)。
- 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること(同条2号)
裁判例

裁判例① リバーサイド事件(東京高判令和4年7月7日)
●事案:
飲食店でパート勤務をしていた労働者が、「そろそろ辞めようかな」と口にしたこと及びシフトを出さなくなり出社しなくなったことをもとに、会社側が「退職の意思あり」と判断し、退職扱いにした事案。
●判決:
裁判所は、「明確な退職の意思表示があったとはいえない」「会社側も確認義務を果たしていない」として、退職処理を無効と判断しました。
●ポイント:
- 雇止めや退職は、本人の意思が明確に示されていなければ無効となる可能性が高い
- 使用者側が一方的に解釈して終了させること認められないとなる可能性が高い
裁判例②東芝柳町工場事件(最判昭和49年7月22日)

これは、雇止めをめぐる判例の代表格であり、後の労働契約法19条にも大きな影響を与えました。
●事案:
契約期間を2か月とする労働契約を結んだ臨時工が、5回ないし23回の労働契約の更新を継続していたにもかかわらず、あるとき突然契約を更新しないと言い渡された。
●判決:
- 本件労働契約は、期間の満了毎に当然に契約の更新を重ねることによって、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものであるとされた
- 臨時工に対する傭止めの効力の判断にあたり解雇に関する法理を類推すべきとされた
●ポイント:
- 更新回数が多い(長年勤務している)ことから、臨時工の雇止めは無期の雇用契約の労働者の解雇と同視できるとされた
裁判例③ 日立メディコ事件(最判昭和61年12月4日)
これも、雇止めをめぐる判例の代表格であり、後の労働契約法19条にも大きな影響を与えました。
●事案:
臨時員として契約期間2年間とする有期労働契約を5回にわたり更新されて勤務していた労働者に対して、業務の見直しを理由に更新拒否(雇止め)が通知された。
●判決:
- 臨時員と会社の雇用関係は、ある程度の雇用の継続が期待されたものであるから、臨時員を契約満了により雇止めする場合解雇に関する法理が類推される
- しかし臨時員は比較的簡易な採用手続きであるため終身雇用の期待の元期間の定めのない労働契約を締結した本工を解雇する場合とは差異がある
→ 結果として、雇止めは有効
●ポイント:
- 期間の定めのない労働契約と実質的に異なる可能性がある場合でも労働者が更新を期待することに合理性が認められる場合、解雇に関する法理が類推適用される。
裁判例④ 日本郵便(苫小牧支店・時給制契約社員B雇止め)(札幌高判平成26年3月13日)

●事案:
郵便事業株式会社に時給制契約社員として、雇用期間を6か月とする雇用契約を8回更新し4年間継続して雇用されていた労働者が、会社の経営改善を理由に雇止めをされた。
●判決:
- 労働者は雇用契約が更新されるものと期待することに合理的理由があるといえるので、解雇に関する法理が類推される
- 解雇の合理性は、※整理解雇の4要件によって判断される。
※①人員削減の必要性
②解雇回避努力の相当性
③人選の合意性
④手続の相当性
- 本件雇止めは、整理解雇の4要件を満たすとして合理性が認められた。
●ポイント:
- ⅰ苫小牧支店は、希望退職者を募った後で、労働時間の短縮による調整をし、その後で本件雇止めをしたこと
ⅱ上記について説明し、意向調査書に必ずしも契約を更新できるとは限らない旨記載されていたこと
以上の事実から、雇止め回避努力を尽くしたと判断された。 - 労働時間の短縮に応じなかった者から優先して雇止めの対象者となる旨の方針の説明がなかったことは、労働者としても労働時間の短縮に応じなかった者から優先して雇止めとなることは容易に認識できたとして、雇止め回避義務の判断に影響を与えないとした。
どのような場合に雇止めを争える?

雇止めが無効とされやすい特徴
- 更新回数が多く、実質的に期間の定めのない雇用契約に近い
- 契約書に更新の可能性があると明示されている
- 雇止めの理由が不明確・口頭のみ・説明なし
このような場合、争える可能性が高いため、ぜひ弁護士にご相談ください、
どうやって争えばいいの?

争う手段としては、
- 交渉(裁判所を使わずに任意で交渉を行う)
- 労働審判
- 裁判
があります。
いずれの方法でも、弁護士を介入させることで円滑な解決が期待できます。
まとめ

- 労働契約法19条は、合理的理由や社会通念上の相当性がない雇止めはできないと規定している
- 有期の雇用契約の雇止めでも、無期の労働契約の解雇の場合と同様に争える場合がある
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
令和2年3月 千葉大学法政経学部法政経学科 卒業
令和4年3月 東京都立大学法科大学院 修了
令和7年4月 弁護士登録