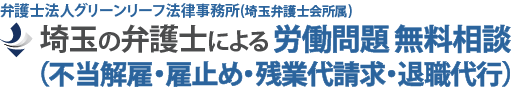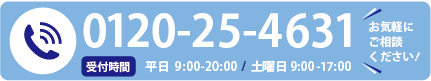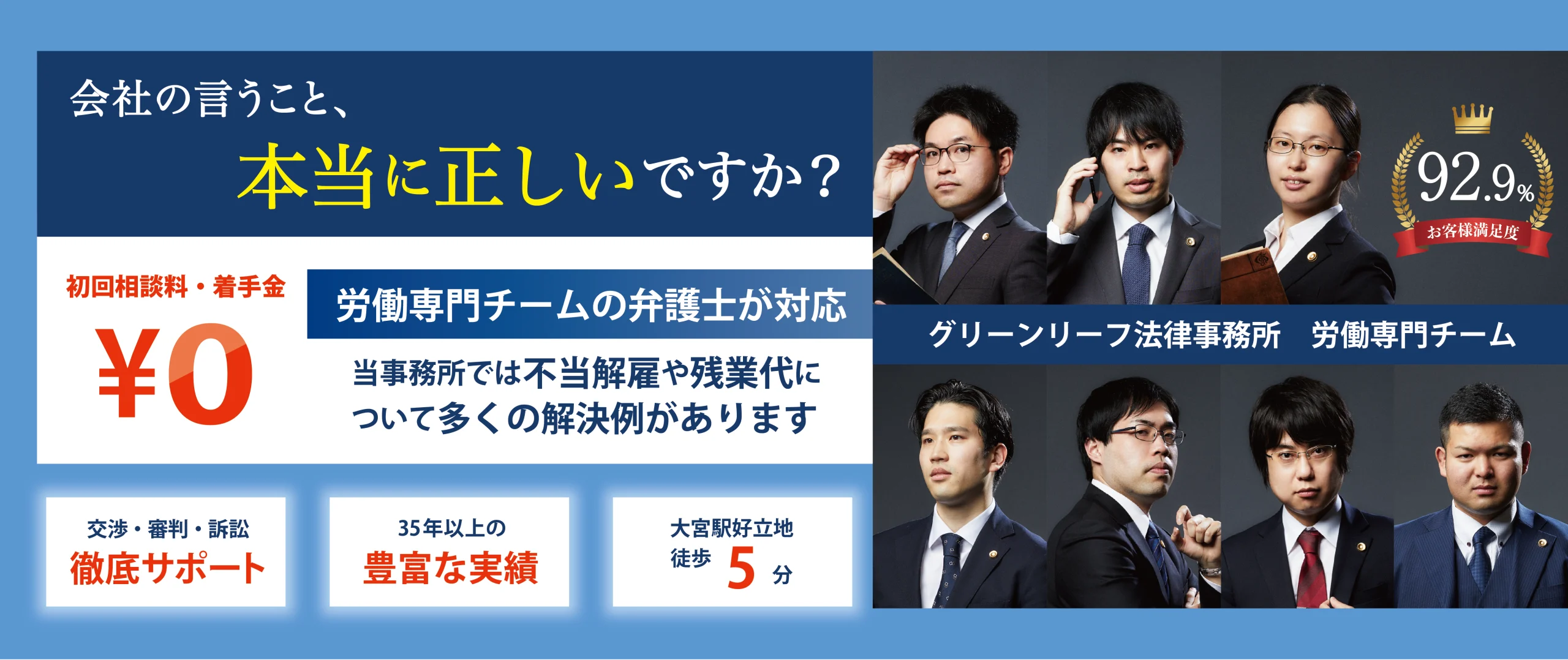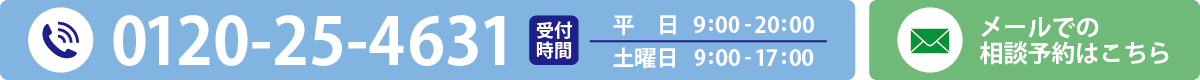「勤務成績が振るわなかったことを理由に解雇されてしまった」、「不祥事を起こしてしまったが会社をクビにされるのには納得がいかない」という方に向けて、この記事では、裁判例を素材に解雇が無効になる基準について解説します。
解雇には無効になる場合がある
使用者による解雇は、裁判例において無効と判断されているものが多くあります。
労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効」であることを定めています。
また、労働契約法15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めて、懲戒権の究極である懲戒解雇を規制しています。
裁判例においては、これらのルールに沿って解雇が無効とされてきました。
解雇が無効になった裁判例
勤務態度が不良な従業員であっても解雇が無効になった裁判例(社会福祉法人蓬莱の会事件・東京高判H30.1.25)

・事案の概要
特別養護老人ホームに勤務していたある従業員は、同老人ホームの中でも認知症の進んだ重症度の高い施設利用者を対象とする部署に異動となった後、以下の事情等を理由に解雇されました。
・上司の業務上の指示命令に従おうとせず、不満を露わにし、施設利用者に聞こえるのも意に介さず、しばしば大声を出し、机を叩くなどといった威圧的な態度を示すことがあった
・その従業員を模倣して上司の指示命令に従わない若い職員も出てきた
・その従業員による反発や粗暴な言動を受け続けた上司は、萎縮し、ノイローゼ気味になり、同じ職場で働くことはできないと訴えるようになったこと
会社側は、従業員に対して、デイサービス部門への配置転換や再就職支援金を受け取って任意退職をすることを打診していましたが、従業員はこれを拒否しました。
・裁判所の判断
裁判所は解雇を無効としました。
その主な理由は、以下のとおりです。
すなわち、解雇は従業員に重大な不利益を与えるから、ただ勤務態度が悪いだけでは解雇はできない。問題の従業員についてデイサービス部門への配置を打診したにとどまり、これを超える措置(実際に配置転換をする等)をとっていなかったから、解雇以外の方法(解雇回避措置)を十分に尽くしていないため解雇に客観的に合理的な理由があるとは認められない、という趣旨のものでした。
・この裁判例からわかること
この裁判例によれば、解雇というのは、従業員に対する最終手段であるということがわかります。
たとえ勤務態度が良くなかろうとも、直ちに解雇が許されるのではなく、上司からの指導や配置転換等、他の手段が用いられた後でなければ解雇は無効となる余地があります。
特に、本件の従業員は、勤務態度が異動後に不良となったために、環境の変化や上司との関係性が起因していたとみられ、従業員だけが悪いといえない事例でした。
また、この裁判例では、会社側が従業員にデイサービス部門への配置転換を打診(提案)していたとしても、他の部署に配置することは出来たのに、具体的にその他の部署や他の上司の下への配置転換を検討したり、実際に配置転換を命じたりしていないために、「解雇回避措置を十分に尽くしていない」として解雇を無効にしたことにも特徴があります。
会社は、業務に関して従業員同士のトラブルが生じたときに、そのトラブルを解決する責任を負っていますので、その責任を会社が十分果たさないのに、トラブルを理由として従業員を解雇することはできません。また、解雇を言い渡された方は、会社が解雇の通知までに配置転換や上司からの適切な指導などがあったか否かをよく確認されることをお勧めします。
勤務能力に不足があることを理由とする解雇が無効になった裁判例(日本アイ・ビー・エム事件・東京地判H28.3.28)

・事案の概要
原告となったX1とX2、X3はそれぞれ長期雇用下の正規従業員として長年会社で勤務してきましたが、勤務成績が不良であることを理由に解雇されました。この従業員は社内の勤務成績を相対的に評価するシステムにおいて低い数値を出し続けてしまったようです。
・裁判所の判断
裁判所は、解雇を無効としました。
そして、勤務成績が不良な者であるとしても、その者の適性に合った職種への転換や業務内容に見合った職位への降格、一定期間内に業務改善が見られなかった場合の解雇の可能性をより具体的に伝えたうえでの業務改善の機会の付与などの手段を講じることなく解雇をしたことについて、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないため無効としました。
・この裁判例からわかること
適性に合った職種への転換とは、従業員それぞれにとってより良い勤務成績を出すことができる部署に配置することなどをいいます。また、業務改善の機会の付与とは、勤務成績が良くない従業員に対して上司が、勤務成績をよくするためにはいかなる手立てをとるかを話し合い、指導するようなことをいいます。
本件の事実関係でも、勤務成績を改善する手立てを会社側もとっていましたが、より具体的に勤務成績が不良であれば解雇の可能性があることを示して勤務成績の改善を働きかけていなかったようです。また、従業員らの職位の降格もなかったようです。
したがって、上記の裁判例は、これらの措置を取らないでする従業員の解雇は無効になるということを意味し、勤務成績が悪いだけでいきなりクビにされた場合には解雇が無効になる可能性があるということがわかります。
セクハラ行為を理由とする解雇が無効になった裁判例(東京地判H24.4.24)

・事案の概要
原告となった従業員は、複数の部下に対して、宴会の際に自身の側に座らせて酌をさせる、ある部下には「犯すぞ」などと申し向けたこと、日常的に酒席において、女性従業員の手を握ったり、肩を抱いたり、それ以外の場面でも、特に、女性の胸の大きさを話題にするなどセクハラ発言も繰り返していました。
また、この従業員は、会社の中でも幹部としての地位にあり、かつ会社内の倫理綱領制定の趣旨・重要性をよく理解していたはずであったのだから、セクハラを防止すべき立場にありました。それにもにもかかわらず、セクハラをしていました。
そしてこの従業員は、上記の事由を理由に解雇されました。
・裁判所の判断
裁判所は、これらの事実について、会社の就業規則上の懲戒事由に当たると判断しました。
一方で、その従業員の解雇は無効であると判断しました。
その理由として、セクハラ行為は「強制わいせつ的なもの」(現在では不同意わいせつ)にあたる程度でないことに加え、「犯すぞ」という言葉は真の意思に基づくものではないこと、その従業員は会社に対して相応の貢献をしてきており、反省の情も示していること、これまで、原告に対して、セクハラ行為についての指導や注意がされたことはなく、いきなり本件懲戒解雇に至ったものであること等の事情を指摘しました。
そのうえで、懲戒の対象になるセクハラ行為は明らかで、しかもコンプライアンスの重要性からしてもセクハラ行為に厳しく対処することが望ましいとしても、会社が従業員に対して何らの指導や処分をせず、労働者にとって極刑である懲戒解雇を直ちに選択するというのは、重過ぎるという趣旨の判断をしました。
・この裁判例からわかること
この裁判例は、セクハラ行為を理由として懲戒解雇を行う際にも、その判断は慎重になるべきとの考え方に基づいています。
また、この事件の従業員は、会社への貢献や反省があることに加え、今まで会社側からセクハラ行為に対して指導や処分を受けてきませんでした。このような事情に裁判所は注目しました。
さらに、この裁判例の興味深いポイントは、会社が当初従業員に伝えていた解雇理由と実際に裁判上で主張した解雇理由が異なることです。
本件の会社は、従業員を解雇した当初、裁判において主張したセクハラ行為に加えて、部下へのパワハラ、会社の与信管理規定違反により会社に600万円の損害を与えたこと、幹部含む他の従業員を威圧したことを解雇の理由にしていました(本判決ではこのことが判決文に記載されています。)。なお、解雇理由証明書などでこれらの解雇理由を知ることができます。
しかし、会社側は、裁判でこれらの理由を主張しませんでした。
一般的に、会社側が解雇の理由を裁判で主張をしない事情には様々なものが推測されます。時には、証拠がなかった、そもそも事実無根であったために、会社が裁判で主張をしない解雇理由もあります。上記の裁判例でなぜ解雇理由の一部が主張されなかったのかは不明ですが、少なくとも会社の言うとおりに解雇を受け入れるべきではない場合も存在することがわかります。
まとめ
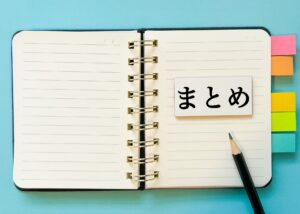
以上の3つの裁判例はそれぞれ、解雇を無効とした裁判例ですが、従業員を解雇する場合には解雇の有効性を厳しく審査しています。例えば、最後に挙げた東京地裁平成24年4月24日判決は、「労働者にとって極刑である懲戒解雇を直ちに選択するというのは,やはり重きに失するものと言わざるを得ない」と表現していますように、労働者にとって最も重い罰が解雇ですので、この判断は慎重にされるべきということです。
会社を解雇されたとしても、解雇を争うことができます。また、会社に残るつもりがなくとも、解雇が無効なのであれば、会社との交渉において有利になります。
解雇が無効になるか否かは、詳細な事情によって判断が分かれてしまいますが、解雇を争う余地がある場合も多く存在しますので、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小松原 柊
令和4年3月 中央大学法学部法律学科 卒業
令和6年3月 東北大学法科大学院 修了
令和7年4月 弁護士登録