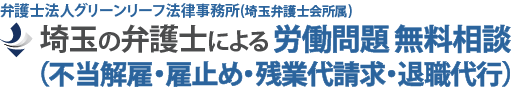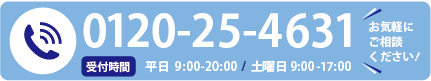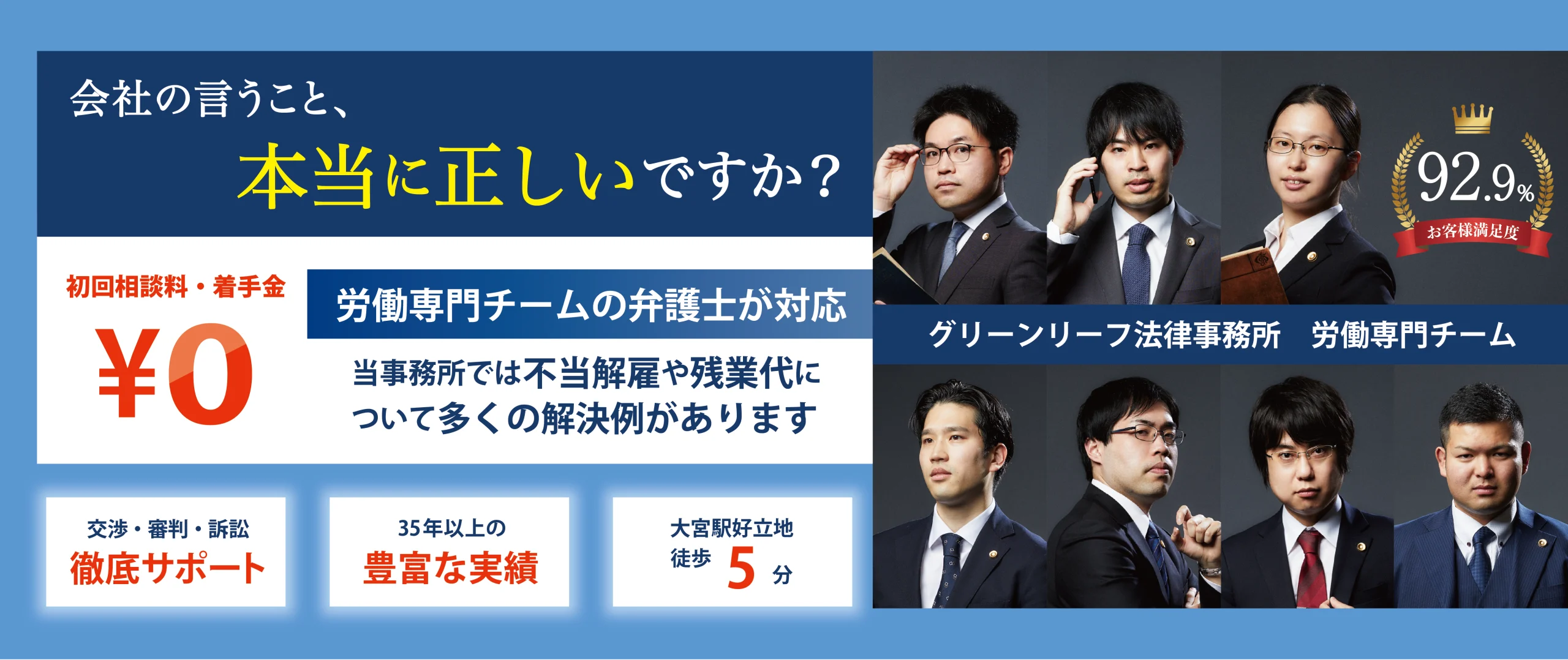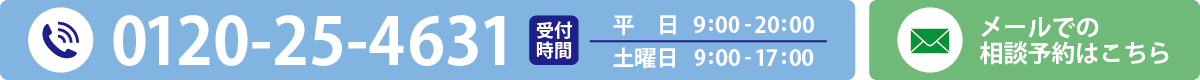企業における新規採用の多くは「試用期間付き」で行われます。これは労働者の適格性や勤務態度、能力などを見極めるための期間であり、期間終了後に本採用の可否が判断されます。
しかし、試用期間後に「本採用を拒否する」ことは、法的にはどこまで認められるのでしょうか。ここでは試用期間経過後の本採用拒否について解説いたします。
試用期間とは?
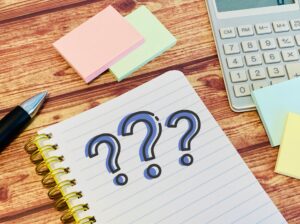
試用期間は、労働者の適格性や勤務態度、能力などを見極めるための期間であり、期間終了後に本採用の可否が判断されます。
試用期間中は雇用契約の一部であり、労働者の不適格事由が発覚した場合等に解約できる権利を留保している状態です。
つまり、試用期間も労働契約は成立していることになります。
裁判例で見る本採用拒否の判断基準

裁判例:三菱樹脂事件(最判昭和48年12月12日)
●事案:
原告は3か月の試用期間付きで被告に採用されたものの、原告が学生運動に従事していたことを隠していたことを理由に試用期間の満了直前に本採用を拒否された事案。
●判決:
- 本採用の拒否は、留保解約権の行使であり、通常の雇入れの拒否とは同視できない
- 本採用の拒否は、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の事由が認められている
- 本採用の拒否は、解約権留保の趣旨、目的に照らし、客観的に合理的理由が存し、社会通念上相当と認められる場合にのみ許容される
●ポイント:
- 解約権の留保は、採否決定の当初では適格性の有無について必要な調査を行い、
適切な判定資料を十分に募集できないため、後日における調査や観察に基づく最終決
定を留保する趣旨でなされたものであるため、本採用の拒否は、通常の解雇よりも広
い範囲で解雇の自由が認められている。
- とはいえ、企業が労働者より社会的地位が優越していること、労働者は当該企業
との雇用関係の継続を期待し他企業への就職の機会と可能性を放棄したものであることから、本採用の拒否は無条件に認められるものではない。
裁判例:神戸弘陵学園事件(最判平成2年6月5日)
●事案:
原告は被告である学校に常勤講師として採用された。その際に契約期間は一応1年間とし、1年間の勤務状態を見て再雇用するか否かの判断をするという説明を受けた。
1年後、労働契約の期間満了したとの通知が原告に出された事案。
●判決:
- 雇用契約に期間を設けた場合、その趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、期間満了により契約が当然に終了する旨の当事者の明確な合意があるというような特段の事情がある場合を除き、その期間は試用期間と解する。
- 解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められている。
- 解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らし、客観的に合理的理由が存し、社会通念上相当と認められる場合にのみ許容される。
●ポイント:
- 三菱樹脂事件と同様に、本採用の拒否は、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の事由が認められている。
- 三菱樹脂事件と同様に、解約権留保の趣旨、目的に照らし、客観的に合理的理由が存し、社会通念上相当と認められるか否かによって、本採用の拒否の適法性を判断している。
- 雇用契約に期間を設けた場合、その期間の性質については、期間を設けた趣旨及び目的から判断する。
違法とされやすい本採用拒否の例

- 能力や勤務態度についての十分な指導・評価機会がなかった
- 単なる「上司と合わない」「主観的評価」に過ぎない
- 業務内容の変更や使用者側の事情による一方的な解雇
- 解雇理由が後付け・形式的である場合
企業としてやるべきことをやらなかったという場合には、違法な本採用拒否となりやすい傾向にあります。
違法とされにくい本採用拒否の例

- 試用期間中、安全に関わる危険な行為を繰り返し、以後もミスを繰り返した
- 配慮を欠いた言動により取引先や同僚を困惑させ、指導や注意にも従わない
このような場合には、違法な本採用拒否とはされにくい傾向にあります。
どのようなケースであれば、争うことができるのかというのは、事案ごとに千差万別です。もしお悩みの場合には、まずは一度弁護士に相談いただけますと幸いです。
試用期間後の本採用拒否であっても、手続きは重要

- 本採用拒否は、法律的には「解雇」に当たるため法律上の解雇の手続規制が及ぶ。
- 使用者に30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払い義務あり(労基法20条)
- 解雇理由について書面の交付を要求すると、使用者は解雇理由証明書を交付する義務がある。(労契法22条2項)
本採用拒否も、法的には解雇に当たるため、解雇と同様の手続きを行う必要があります。こうした手続に不備があることを捉えて、会社側に主張をすることも考えられます。
労働者側の対処法と相談先

- 不当な本採用拒否は労働審判等で争える余地がある。
- 本採用拒否は違法であるとして、労働者としての地位の確認やその間の賃金の支払いを求めることができる。
- 本人の勤務実態・評価記録・入社時の約束事の証拠化が鍵。
- まず労働者は、使用者に対し、解雇理由について証明書の交付を要求することが大事。
- 本採用拒否された場合、早期に弁護士相談を。
まとめ:「試用期間後の本採用拒否だからといって諦めてはならない」
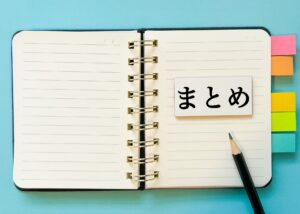
- 試用期間後の本採用拒否は、法的には通常の雇い入れではなく「解雇」である。
- 本採用拒否をするには、本採用の拒否に客観的に合理的理由が存し、社会通念上相当と認められることが必要である。
- 労働者は、本採用拒否された場合、早めに弁護士に相談することが重要。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
令和2年3月 千葉大学法政経学部法政経学科 卒業
令和4年3月 東京都立大学法科大学院 修了
令和7年4月 弁護士登録