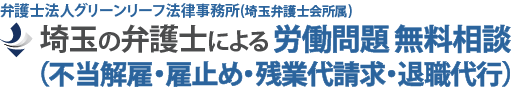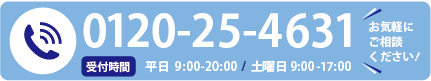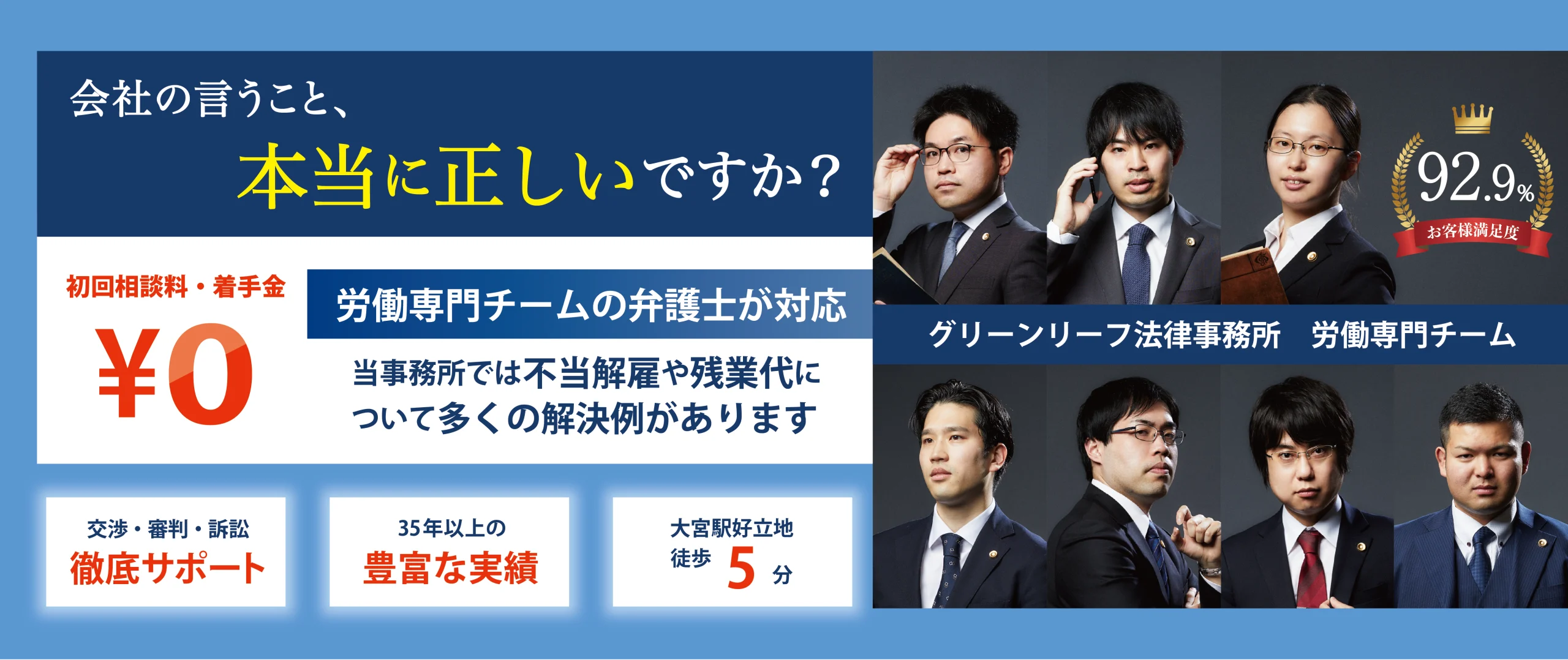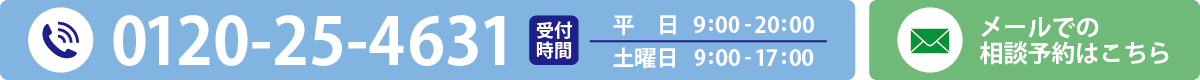労働者が注目すべき育児・介護休業法の改正点を整理しました。子どもの看護休暇の対象の拡大、所定外労働制限の対象拡大、テレワーク、柔軟な働き方の措置等、子育てと労働の両立に役立つ重要な内容ですので、ご紹介をさせて頂きます。
育児・介護休業法の改正(2025年4月1日 & 10月1日施行)
2025年4月施行のものと、同年10月施行のものがありますので、順番にご紹介いたします。
2025年4月1日施行の内容

子どもの看護休暇の対象範囲の拡大
対象となる子の範囲が、改正前は小学校就学の始期に達するまでだったのですが、小学校3年生修了までに延長されました。
また、休暇の取得事由として、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が追加
されました。
そして、労使協定の締結により、制度から除外できる労働者が、「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみに変更されました。
所定外労働の制限の対象範囲の拡大
所定外労働の制限(残業免除)が、改正前は3歳未満の子を養育する労働者だったのですが、小学校就学前の子を養育する労働者にまで拡大されました。
テレワーク
3歳未満の子を養育する労働者に関し、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置として、法改正によりテレワークが追加されました。
また、法改正により、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。
育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
育児休業取得状況の公表義務が、法改正前は1,000人超企業だったのですが、改正により300人超企業にまで拡大されました。
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合です。
2025年10月1日施行の内容

3歳以上の小学校就学前の子を養育する人を対象とした柔軟な働き方の措置
法改正により、事業主には、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者について、柔軟な働き方を実現するための措置を行うことが義務づけられます。
事業主は、次の①~⑤の措置の中から、2つ以上の措置を選択して講じなくてはなりません。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(月に10日以上)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(年に10日以上)
⑤短時間勤務制度
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することが可能です。
なお、事業主が措置を選択する際は、過半数組合等から意見を聴取する機会を設けなくてはなりません。
また、事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの時期に、次の事項の周知と、制度利用の意向確認を個別に行わなければなりません。
周知の時期 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
周知する事項
①事業主が上記で選択した措置(2つ以上)の内容
②利用する措置の申出先(例:総務部など)
③所定外労働(残業免除)、時間外労働、深夜業の制限に関する制度
周知及び意向確認の方法
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
※①はオンラインでの面談も可能。③及び④は労働者が希望する場合のみ
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取及び配慮

法改正により、事業主は、妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取を義務づけられました。
仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。
意向聴取の時期
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
聴取する内容
①勤務時間帯(始業・終業時刻)
②勤務地(就業場所)
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業条件(業務の量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか
※①はオンラインでの面談も可能。③④は労働者が希望する場合のみ。
まとめ
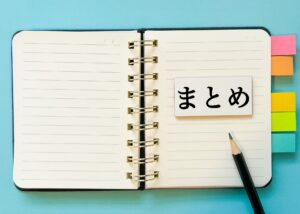
以上の通りご説明をさせて頂きました通り、2025年は育児・介護休業法の改正によって、事業主において、労働者が子育てと労働を両立させるために、様々な措置を行う必要が生じます。これらの措置は、労働者が子どものために休暇を取りやすくなったり、労働時間を短縮したり、事業所へ通勤する必要がなくなる等、労働者にとって役立つものです。労働者の皆様においては、これらの措置の内容を理解し、ご自身の子育てと労働を両立させるための手段を講じて頂くのが良いと思います。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。