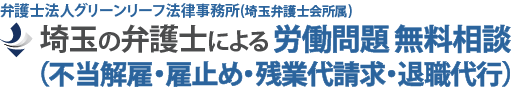懲戒解雇は、労働者にとって「死刑宣告」とも言われるほど重い処分です。しかし、会社が下した懲戒解雇が法的に有効であるケースは少ないです。懲戒解雇が有効とされるための厳しい条件と、不当な処分に立ち向かうための具体的なステップを詳細に解説します。
懲戒解雇はなぜ「簡単にはできない」のか

日本において、労働者は法律によって強力に守られています。会社側が「社内規定に書いてあるから」「重大な違反だから」と一方的に主張しても、それが直ちに法的に認められるわけではありません。
根拠となるのは、労働契約法第15条です。
労働契約法第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、その原因となる労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該処分は無効とする。
この条文にある「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という2つの言葉が、労働者にとっての防波堤となります。懲戒解雇が有効になるためには、会社はこの2つの壁を完全にクリアしなければなりません。実務上、この壁は非常に高く、経営者が考えている以上に懲戒解雇のハードルは高いのです。
懲戒解雇が有効とされるための「厳格な4要件」

裁判所が懲戒解雇の有効性を判断する際、主に以下の4つのポイントを厳格にチェックします。これらの一つでも欠けていれば、その解雇は「不当解雇(無効)」となる可能性が極めて高くなります。
① 罪刑法定主義の原則(就業規則の明記)
懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則に「どのような行為をすれば、どのような懲戒処分を受けるか」が具体的に記載されていなければなりません。また、その就業規則が労働者に周知されている(いつでも見られる状態にある)ことも必須条件です。 規則にない理由を後から持ち出したり、周知されていないルールを根拠に解雇したりすることは、いわゆる「後出しジャンケン」であり、法的に許されません。
② 客観的な事実の証明(真実性の原則)
解雇の理由となった事実が、本当に行われたのかという点です。「〇〇さんが言っていた」「あいつならやりかねない」といった推測や伝聞では足りません。
いつ、どこで、どのような行為をしたのか
その行為によって会社にどのような具体的損害が出たのか これらを会社側が客観的な証拠(メール、ログ、録音、目撃証言、入出金記録など)によって証明する必要があります。もし疑いがある段階で解雇を強行したのであれば、それは事実誤認による不当解雇となります。
③ 処分の相当性(均衡の原則)
ここが実務上、最も争点になるポイントです。懲戒解雇は、数ある懲戒処分(戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、普通解雇など)の中で、最も重い「極刑」です。 「過去に一度も問題を起こしたことがない社員が、一度だけミスをした」というケースで、いきなり懲戒解雇を選択することは、処分のバランスを著しく欠いています。これを「酷にすぎる」と判断されれば、解雇は無効になります。
④ 手続きの正当性(適正手続の保障)
いくら重大な不祥事があったとしても、会社が一方的にクビを宣告することはできません。対象となる労働者に「弁明の機会(言い分を聴く機会)」を与え、本人の主張を十分に聞き取るプロセスが必要です。また、就業規則に「懲戒委員会を開催する」と定められている場合は、その手続きを適正に経ている必要があります。
「そんな要件は満たさない」ケースが圧倒的に多い

さて、ここで重要な事実をお話しします。実際にご相談いただくケースの多くは、上記の要件を到底満たしていません。多くの会社は、懲戒解雇を「嫌いな社員を合法的に追い出す手段」や「ミスに対するペナルティ」程度に軽く考えていますが、裁判所はそうは認めません。
以下のようなケースで懲戒解雇を言い渡されたなら、それは高確率で「無効」です。
ケースA:軽微な業務ミスや能力不足
「仕事で大きな発注ミスをした」「営業成績が著しく低い」「指示した書類作成ができない」。これらは、基本的には「普通解雇」の検討材料にはなり得ますが、懲戒解雇の理由にはなり得ません。懲戒解雇はあくまで「企業秩序を著しく乱す悪質な行為」に対する制裁だからです。
ケースB:上司への反抗や態度の悪さ
「上司に口答えをした」「職場の雰囲気を悪くしている」。これらも感情的な対立に過ぎないことが多く、よほどの暴行や執拗な嫌がらせがない限り、懲戒解雇を正当化する理由にはなりません。
ケースC:私生活上のトラブル
勤務時間外にSNSで不適切な投稿をした、私生活で借金をした、あるいは痴漢等で逮捕された(示談成立済み)といったケースです。会社の名誉を著しく失墜させたといえる特別な事情がない限り、私生活の動向は懲戒解雇の理由としては極めて弱いです。
ケースD:一度きりの失敗で、事前の指導がない
どれほど重大なミスであっても、会社側がこれまで一度も注意指導を行わず、改善の機会を与えていなかったのであれば、いきなりの懲戒解雇は「相当性」を欠くとみなされます。
懲戒解雇を言い渡されたら、まずすべきこと(自己防衛策)

会社から「懲戒解雇」を告げられた直後は、パニックになり、冷静な判断が難しくなります。しかし、その瞬間の対応が、後の裁判や交渉の行方を大きく左右します。以下の4点を必ず守ってください。
① その場で安易に書類にサインしない
会社は「今サインすれば退職金を少し出す」「自己都合退職にしてやる」と甘い言葉で、あるいは「認めないと刑事告訴する」と脅し、合意書や退職届にサインを求めます。 しかし、一度サインしてしまうと「納得して辞めた」とみなされ、後から覆すのが至難の業になります。「動転しているので、一度持ち帰って弁護士に相談します」とだけ言い、その場を離れてください。
② 解雇理由証明書を請求する
口頭で「クビだ」と言われただけでは、会社は後からいくらでも理由を捏造できてしまいます。労働基準法第22条に基づき、会社に対して「解雇の理由を詳細に記した書面(解雇理由証明書)」を即座に請求してください。会社はこれを拒否することはできません。
③ 証拠を保全する
会社から締め出される前に、以下のものを確保できる範囲で確保してください。
- 就業規則の写し(特に懲戒の規定)
- これまでの評価がわかる資料(査定の結果、表彰など)
- 上司とのやり取り(メール、チャット、LINEのスクリーンショット)
- 解雇を言い渡された際の録音(スマホの録音機能で十分です)
④ 「出勤の意思」を示し続ける
会社から「明日から来なくていい」と言われても、メールなどで「私は働く意思があります。解雇に納得していないので、明日の業務指示をください」と送っておくことが重要です。これにより、後の裁判で「解雇期間中の賃金(バックペイ)」を請求できる権利が守られます。
弁護士に相談することで得られる「本当のメリット」

「弁護士に頼むのは大ごとすぎる」「お金がかかる」と思われるかもしれません。しかし、懲戒解雇を突きつけられた労働者にとって、弁護士は単なる「法律の代弁者」以上の役割を果たします。
精神的な盾になる
会社との直接交渉は、人格を否定されるような言葉を投げかけられることもあり、非常に苦しいものです。弁護士が代理人になれば、あなたは会社と直接話す必要は一切なくなります。すべての窓口を弁護士が引き受けることで、あなたは心身の平穏を取り戻し、再就職に向けた準備に集中できます。
「解雇の撤回」と「有利な条件での解決」
弁護士が法的な不備を突くことで、会社側は「このまま裁判になれば負ける」と悟ります。その結果、以下のような現実的な着地点を見出すことが可能になります。
解決金の受領
不当な解雇に対する慰謝料や、数ヶ月〜1年分程度の給与相当額を「解決金」として受け取り、合意退職する。
退職理由の書き換え
「懲戒解雇」という経歴を抹消し、「会社都合退職」や「合意退職」に書き換えさせます。これにより、再就職への悪影響を防ぎます。
失業保険の即時受給
懲戒解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇)のままだと失業保険に長い給付制限がつきますが、会社都合に変更することで、待機期間後すぐに受給できるようになります。
バックペイ(未払賃金)の請求
解雇が無効であると判断された場合、解雇されていた期間(裁判や交渉をしていた期間)も「雇用は継続していた」ことになります。つまり、その期間に働いていなくても、会社はあなたに給料を全額支払わなければなりません。これが数十万、数百万円単位になることも珍しくありません。
結びに

あなたは一人ではありません。まずはご相談ください
懲戒解雇を宣告されたとき、人は深い孤独と絶望を感じます。「自分が悪かったのではないか」「もうどこにも雇ってもらえないのではないか」と自分を責めてしまう方も多いです。
しかし、立ち止まって考えてみてください。一つのミスや、一時の感情の対立で、あなたのこれまでのキャリアやこれからの生活をすべて奪う権利が、会社にあるのでしょうか。
日本の司法制度は、そんな理不尽を許しません。私たちが介入することで、事態は必ず動き出します。あなたがこれまでに築いてきた名誉を守り、次のステップへ胸を張って進めるよう、法的な観点から全力でサポートいたします。
まずは、あなたの置かれた状況をお聞かせください。どんなに小さな疑問でも構いません。「これって本当におかしいんじゃないか?」というその直感は、多くの場合、正しいのです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。